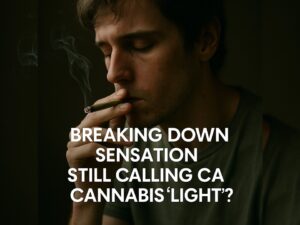朝、目覚める。
けれど、空腹ではない。
それでも「朝だから」と口に何かを運ぶ。
その行為が、いつからか“習慣”として埋め込まれた。だが、そろそろ考え直してもいいのではないかと思うのだ。
本当に、朝食は「必要」なのか──と。
人類の歴史を遡れば、私たちは空腹のまま活動を始めていた。
狩りに出る。
水を汲む。
子どもを背負って山を歩く。
その行為には、満腹では成し得ない軽やかさがあり、朝とは、本来“始まりの身体”が目を覚ます時間。
食べることよりも、
動き出すことが自然だったのだ。
では、なぜ私たちは「朝食が必要」だと信じ込むようになったのか?
答えは、静かに語られる歴史の中にある。19世紀、宗教的思想に基づき「禁欲のための朝食」が作られた。
ケロッグ兄弟が作ったシリアルは、のちに莫大なマーケティングによって 「健康的な朝の選択肢」として普及した。
さらに20世紀、ベーコン業界が仕掛けた「しっかり食べる=ベーコン&エッグ」という幻想。
これらは、身体の声ではなく産業の声だった。
甘い朝食も同様だ。
イタリアのバールに並ぶカプチーノとコルネット。
華やかで、豊かな文化に見えるその習慣も、実は 菓子業界と製糖企業の“育てた朝”だった。
そしてその甘さが、依存の朝を生み出した。
気づけば、私たちは「空腹を感じる前に」「時計と広告に従って」食べている。
それは、本当に“食べたい”という声だったのか?
私は、食べない朝を選ぶ。
空腹を感じるまで、体に任せてみる。
すると、ふと頭が冴える。
胃のあたりに、静けさが戻る。
身体という器が「満たす前に整える」時間を欲していたのだと分かる。
朝食を否定したいわけではない。
ただ、選択肢として“食べない自由”があってもいいと思うのだ。
何も食べずに歩き出せる朝。
それは、社会が押しつけてきた帳をそっと閉じ、 自分だけのリズムで始まる、ささやかな革命である。
朝食という「最初の帳」を焼いたとき、 私たちは初めて、自分の身体の声に耳を傾ける。
そしてまた、食べたいと感じたときに食べればいい。
そのとき、食べるという行為は“義務”ではなく、“感謝”に変わる。
エピローグ
空腹が教えてくれること。
ある日、早朝の街を歩いていた。
パン屋の香りが遠くから漂ってきた。
その瞬間、自分の身体が「今、食べたい」と小さくささやいた。
それは義務でも、スケジュールでもない。
ただ、風の中に香りを感じて、胃が動いた。
そのパンは、とてもゆっくり噛みしめられた。
口にしたとき、思った。「これが、食べるということか」
食欲とは、コントロールでも我慢でもない。
それは、**自然のなかにいる生き物としての
“反応”**だった。
私は、あの日以来ずっと、
“空腹を待つ”という選択を大切にしている。
そして、空腹が教えてくれる朝は、
どんな栄養学よりも、確かに私を整えてくれるのだ。