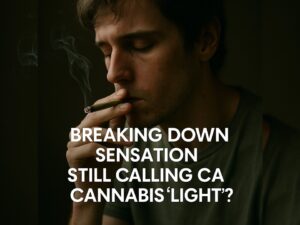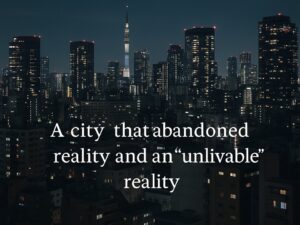夢のなかで、父が歩いていた。
うしろ姿しか見えなかったけれど、あれはたしかに父だった。
ゆっくり歩いていて、何度も振り返りそうで、でも振り返らなくて。
わたしは、その背中をただ、黙って追いかけていた。
父の背中は、いつもどこか遠かった。
家にいても、仕事をしていても、テレビを見ていても、父はどこかに「行こうとしている人」だった。
物静かで、怒らず、笑わず、叱ることもなかった。やさしかったけど、やさしさは、たとえば硬いソファのようだった。
寄りかかれるけれど、包んではくれない。
冷たくはないけど、あたたかくもない。そんな感じ。
「父」としての彼と、「人」としての彼。
その境界が、ずっとわからなかった。
でも、夢のなかの父は、ただの“人”だった。
背中に、名前が書いてあるわけでもなく、
どこかに向かってる気配だけを残して、静かに歩いていた。
目が覚めて、なぜか涙が出た。
なつかしいとか、恋しいとか、そういう感情じゃなくて、
「やっと、追いつけた」みたいな、変な達成感。
でもすぐに気づいた。
わたしは夢の中でも、結局、父の背中に声をかけなかった。
振り返ってほしいのに、呼び止めたいのに、
それができなかった。
たぶん、もう、何かを伝えたかったわけじゃないんだ。
ただ、**「同じ時間を歩いていた」**ってことが、
それだけで、奇跡みたいに思えたんだと思う。
父はもういない。
現実には、会えない。
でも、“背中”っていう不思議な部分だけが、
ずっと、わたしのなかに残ってる。
あれはきっと、「父」じゃなくて、
「自分のなかの父」だったのかもしれない。
わたしが覚えているのは、
父の顔じゃなくて、背中だった。
背中って、最後に残る風景なんだと思う。
人が誰かを追いかけた記憶って、たいてい背中のままだ。
そしてきっと、
自分もいつか、誰かの“背中の記憶”になるんだろう。
🫧 読者への問い
あなたの中に、忘れられない“背中”はありますか?