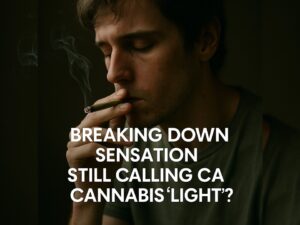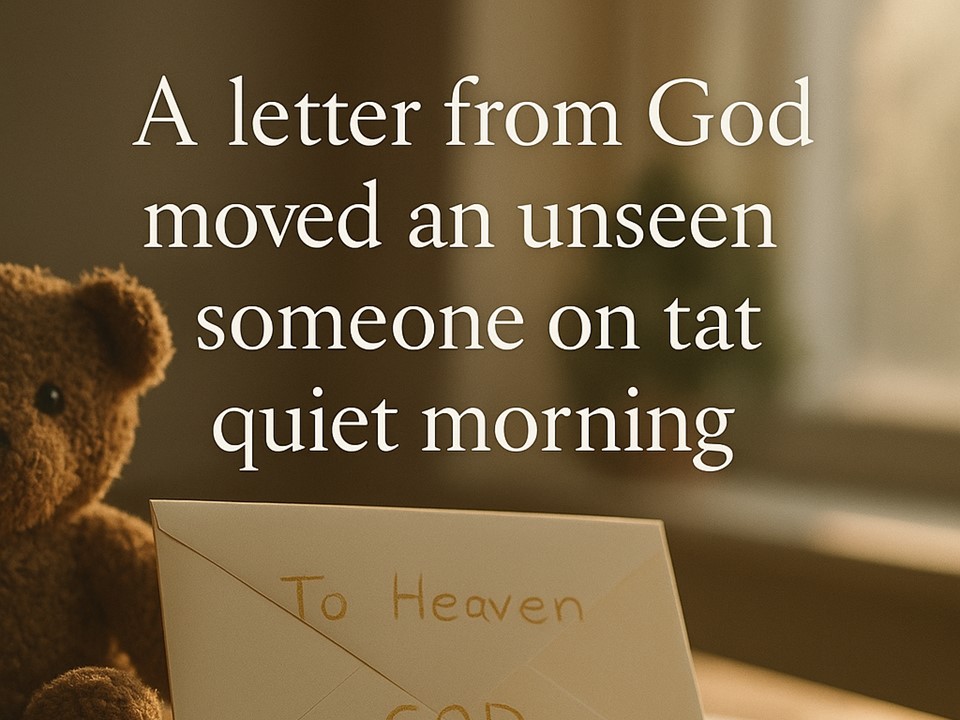
その朝、つものようにスマホを片手に、コーヒーをすすっていた。
何気なく開いたSNSのタイムラインに、一つの投稿がふっと流れてきた。
画面の中の投稿者は、名も知らぬ誰か。
ただ、そこに書かれていた話が、やけに静かに、心の奥へ染み込んできた。
話の主役は、ある少女だった。
お母さんと二人で暮らしている。
小さな胸に、誰にも言えない寂しさを抱えていた。
彼女には“神様”がいた。
けれど最近、その神様が何だか遠くなった気がして、ある朝つぶやいたのだという。
「神様って、本当にいるの?」
その問いに、お母さんは言葉を選びながら答えた。「……もしいるなら、手紙を書いてみたらどうかな?」
少女は真剣な顔でうなずいた。
翌朝、ランドセルに小さな封筒が入っていた。
宛先には、たった一言。
『かみさまへ』
手紙の内容は、投稿には書かれていなかった。
けれどその後の展開だけで、十分に想像ができた。
母親はその手紙を、実際に郵便ポストに投函したのだという。
「これは届かないよ」とは言わずに。
数日後。
少女の元に、見知らぬ差出人からの返事が届いた。
それは“神様”からの返事だった。
筆跡は丁寧で、言葉は優しく、子どもにもわかるように書かれていた。
「○○ちゃん、手紙ありがとう。ちゃんと届いたよ。君のことはずっと見ている。
悲しい日も、嬉しい日も、君はひとりじゃない」
読み終えた少女は、しばらくその便箋を抱きしめていたという。
投稿には、
それ以上のことは書かれていなかった。
でも私は、涙が止まらなかった。
胸の奥に何かが熱く広がり、
その日から、見知らぬ誰かの優しさが、
日常の空気を少しだけ変えた。
誰が返事を書いたのかはわからない。
郵便局の人かもしれないし、母親が誰かに頼んだのかもしれない。
あるいは、本当に神様だったのかもしれない。
けれど、その「誰か」が動いたこと。
そして、母親が“信じる行動”を選んだこと──
それがすべてだった。
私は、この話を誰かに話したくなった。
でも、うまく言葉にできる自信がない。
だから、こうして文章にして残す。
「見えない誰かの優しさは、確かに届く」
そう信じるだけで、世界は少しだけ、やさしくなれる気がする。
あの日の朝、少女が書いたあの小さな手紙。
それは、誰かの心の中にも、そっと届いていたのだ。
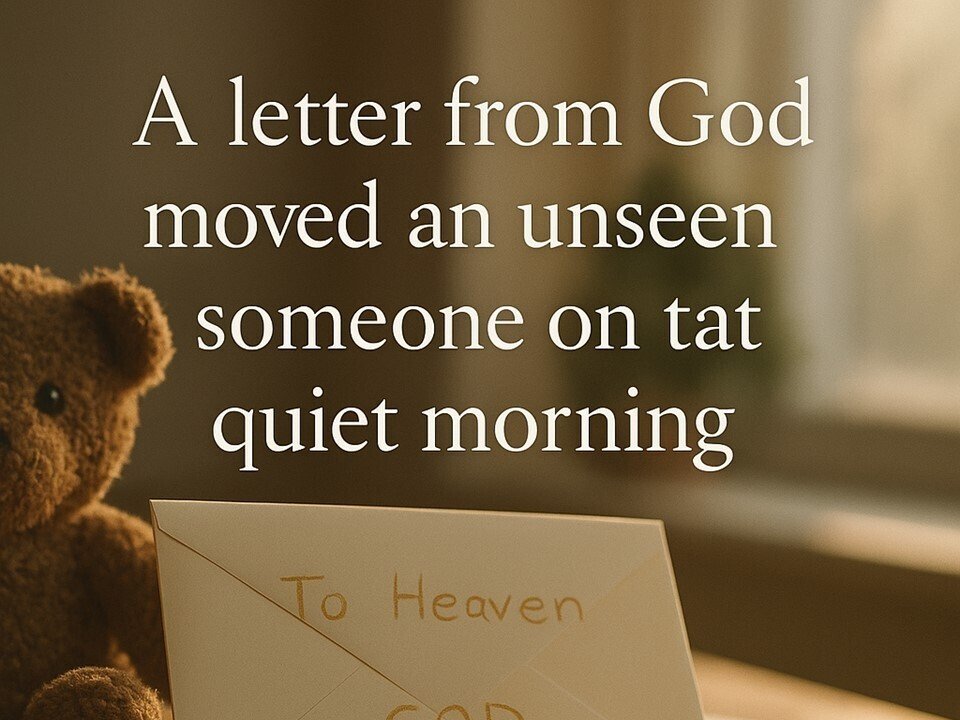
返事が来たのは、ほんとうに必要だった朝だった。