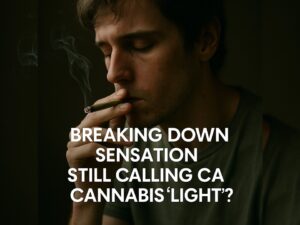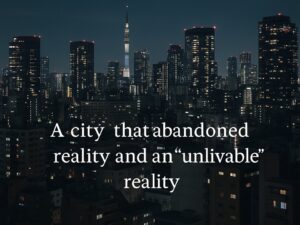副題:言葉にならない優しさが、静かに行き交う場所で
「降ってきたね」
そう言って、見知らぬ人が横に立った。
小さなバス停の屋根の下。
ほんの数分間だけ重なる、私と誰かの時間。
駅まで歩ける距離だけど、濡れたくなかった。
そんな理由で足を止めたのに、
その会話は妙に心に残った。
その人は、60代くらいの女性だった。
小ぶりな傘を持っていたけれど、
開くこともなく「ちょっとだけ、ね」と言って、
私の隣に立った。
「こんなに急に降るなんて、天気予報当たらないわね」私は曖昧に笑った。
でもその人の目はまっすぐで、
まるで“本当は別の話がしたいんだよ”と言っているようだった。
「うちの孫も、最近はあんまり外で遊ばないのよ」
私は驚いた。
いきなり話題が変わった。
でも、そのトーンが妙に優しくて、
つい「今の子たちは、ゲームとかですもんね」と返していた。
そこからぽつぽつ、会話が始まった。
彼女は、近所に住む人らしかった。
長年住んでいたアパートが来月で取り壊されること。 次の住まいがなかなか見つからないこと。
「もう引っ越しも3回目よ。年寄りは面倒がられるの」言葉の端々に、少しだけ力の抜けたような寂しさがあった。
私は頷くしかできなかったけど、
それでもその間、彼女の言葉がまっすぐに心に届いてきた。
雨は止みかけていた。
でも私は、もう少しだけそこにいたかった。
誰かの暮らしの“匂い”みたいなものが、
雨に混ざって、心に染みていた。
バスは来なかった。 で
もその人は、「ありがとうね」と言って、
小さな傘を開いた。
私は「お気をつけて」と言った。
それだけで、なぜか一日がすごくやさしく終われた気がした。
人生には、目的のない時間がある。
でも、だからこそ生まれる会話があって、
その一言が、なぜか後を引く。
雨宿りという名の会話。
それは、日常のどこかに、
まだ人の温度が残っていると気づかせてくれる時間だった……