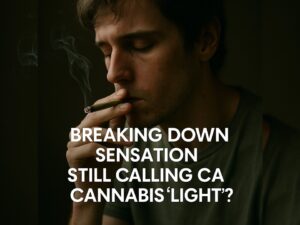その夜、彼女は静かにページをめくった。
母子手帳。
病院でもらったあの冊子は、すでに角がすり切れ、ページには無数の記録が並んでいた。
体温、接種履歴、体重の増減、栄養指導、母親教室の日程──
何もかもが、そこには「正しさ」として書かれていた。
だが、そのどれにも、彼女自身の直感は記されていなかった。
「いつか、この帳を燃やす日が来ると思ってた」
彼女は、そう言った。
焚火台に置かれた鉄皿の上で、ゆっくりと火が広がっていく。
書かれた記録が、音もなく灰になっていく。
母としての恐れ、不安、焦り。誰かの指示に従ってきた日々。
燃えていくページの中に、それらもまた染み込んでいた。
彼女の頬に、風が当たる。
火の粉が空へ舞う。
夜の静けさのなかで、彼女は初めて深く息を吐いた。
私は問いかける。
「なぜ、燃やしたのですか?」
彼女は少し考えてから、笑った。
「ようやく、自分で決めてもいいって思えたから。
帳があったから安心してたけど、帳があるから不安にもなってた。
全部、帳のせいじゃなくて、私の覚悟の問題だったんです」
子どもは近くで遊んでいた。
火を見つめながら、たまに何かをつぶやいている。意味はわからないが、その声には曇りがなかった。
「この子を信じるって、どういうことか分かってきた気がする」
彼女は言う。
「この子の免疫を信じる、回復力を信じる、そして、自分の感じたことを信じる。
それが“育てる”じゃなくて“生きる”ってことなんだと思う」
社会が用意した正しさから一歩はみ出すと、人は不安になる。
だけど、はみ出したところにこそ、「その人だけの輪郭」があるのだと思う。
帳は、安心を与えてくれる。
だが同時に、私たちを“枠”の中に閉じ込めてもいた。
それを燃やすことは、ただの否定ではない。
新しい肯定の始まりだ。
「また、書きますか? 何か別の帳に」
私がそう尋ねたとき、彼女は首を振った。
「もう書かない。記録しない。でも、忘れない」
未来は、数値では測れない。
たしかなものは、手の温度、呼吸の速さ、
夜中の沈黙に宿る気配。
そうしたものの中にしか、未来は芽生えない。
私は見ていた。
燃えた帳の灰が、風に乗って流れていく。
そしてその風に、確かに“始まりの匂い”があった。
帳を焼く日──
それは、また始める日だった…….