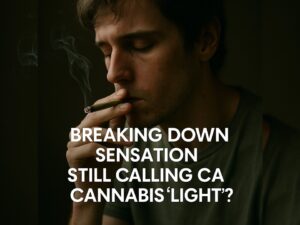人は誰でも、ひとつくらい、誰にも言えない秘密を持っている。
それは恥ずかしい記憶かもしれないし、 胸を焦がした片想いかもしれないし、 誰にも気づかれなかった小さな夢かもしれない。
たとえ今は忘れていても、ふとした瞬間に蘇る。 風の匂い、夕焼けの色、古い曲のイントロ。
心の奥の引き出しには、そんな記憶が鍵をかけたまましまわれている。
小学生の頃、机の引き出しの奥にこっそりノートを隠していた。 そこには誰にも見せたことのない詩や、将来の夢や、 転校していったあの子への手紙なんかを書いていた。
誰かに見られたら恥ずかしくてたまらない。 でも、自分の中でだけは確かに存在していた“わたし”だった。
そのノートはもうないけれど、 その感覚はいまも胸の奥で、あの頃の自分をそっと守ってくれている気がする。
大人になると、日々の生活に追われて、 いつのまにか鍵の場所を忘れてしまう。
誰かの期待に応えるうちに、 社会のルールに馴染むうちに、 本当の自分の気持ちを置いてけぼりにしてしまうこともある。
でもある日、たとえば旅先のホテルで一人でいる夜とか、 何の気なしに開いた古本の一節にふれたときとか、
その鍵が、突然カチリと回る瞬間がある。
思い出すのだ。 忘れていたはずの自分が、ちゃんと生きていたこと。 泣いたこと、笑ったこと、誰にも話さなかった想いのかけらたち。
鍵が開いた先には、 誰にも見せていなかったけど、たしかに存在していた“わたし”がいる。
その“わたし”は、完璧じゃない。 少し不器用で、空気が読めなくて、 人に合わせられなくて、自分を責めたりもするけれど、
それでも、愛おしくて、大事なわたし。
鍵をかけていたのは、 たぶん傷つきたくなかったから。 でも、その鍵を開けてあげるのは、自分自身でしかできない。
今、誰かに話さなくてもいい。 ただ、自分の中に鍵があるってことだけ、 そっと思い出せたら、それで十分だと思う。
人は誰でも、秘密の“鍵”を持っている。 それがある限り、きっとどこかで、自分とまた出会える気がする。
Epilogue
鍵があるかぎり、わたしは、わたしをなくさないでいられる。

それだけで、たぶん、だいじょうぶ。