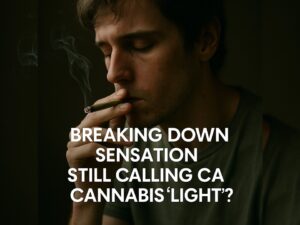──余命7日の老人と、郵便受けに届いた子どもの手紙
その日、老人は朝の光を浴びながら、ゆっくりと椅子に座った。
ベランダ越しに見える小さな桜の木は、すでに花を落としはじめていて、
まるで彼の心の中と同じように静かだった。
「あと7日」
医師はそう言った。
予想よりも、すこし早かった。
けれど老人は、もう驚かなかった。
家族はなく、友も遠のき、声をかける相手もいない。
カレンダーをめくる理由も、もうなかった。
午前11時すぎ、ポストにひとつの封筒が届いた。
裏には見覚えのない名前、そして筆跡。
それは、隣のアパートに住む小学生の男の子からのものだった。
中には、色鉛筆で描かれた拙い手紙が入っていた。
こんにちは。おじいちゃん、いつも同じ時間にベランダにいるね。
ぼく、おじいちゃんが毎日ちゃんといるのがなんか安心するの。
この前、転んだとき、おじいちゃんが『大丈夫か』って言ってくれたの、ぼく覚えてる。
ありがとう。すごくうれしかったよ。
おじいちゃんが見てるから、
ぼく、ひとりでもがんばれる気がる。
ぼくもいつか、おじいちゃんみたいに、だれかを見守れる人になりたいな。 またあしたも、ベランダにいてね。」
手紙を読み終えた老人の手が、わずかに震えた。
何年ぶりだっただろう。
「ありがとう」と言われたのは。
心の奥にしまい込んでいた何かが、
その瞬間、確かにほどけた。
次の日も、彼はベランダにいた。
そのまた次の日も、ベンチに腰をかけ、目を細めて通学路を見つめていた。
不思議なことに、体調は悪化していなかった。
むしろ、少しだけ呼吸が軽くなったようにさえ感じた。
7日が過ぎた。
医師の言葉よりも、春は長く居座った。
老人はその後も毎日、ベランダにいた。
手紙の少年が高校生になっても、
手すりに手をかけ、静かに見守っていた。
そして、桜が再び咲く頃。
ベランダの椅子には、花びらともう一通の手紙が残されていた。
「ぼく、大学に行くよ。
ありがとう、おじいちゃん。
おじいちゃんの“いつも通り”が、ぼくの“ずっとの勇気”でした。」
エピローグ
小さな勇気は、
声をかけることかもしれない。
ただ、そこにいることかもしれない。
それが誰かの人生を変えることが、ある。
この世界でいちばん小さな勇気が、
誰かにとって、いちばん大きな光になることがある。