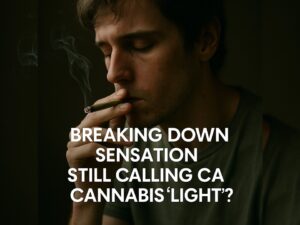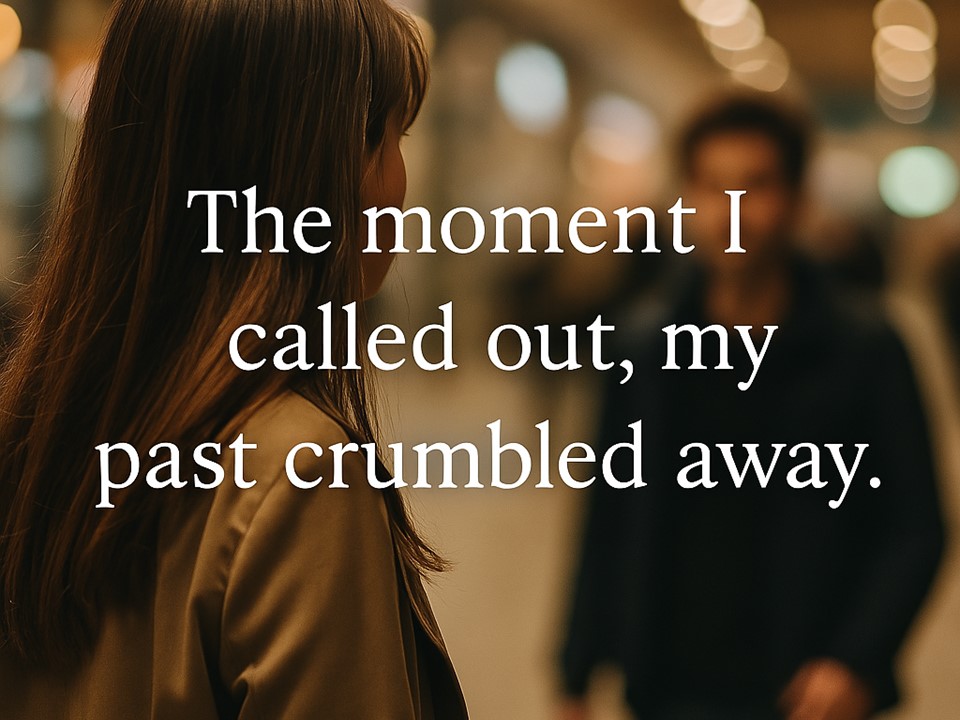
あれは、偶然だった。
でも、あの“偶然”に、ずっとどこかで期待していた自分がいた気もする。
駅のコンコース。
夕方のざわついた空気の中。
すれ違った横顔に、ふと視線が止まった。
懐かしい、というより
**「知っているはずの誰か」**という感覚だった。
名前を呼ぶには勇気が要った。
でも、呼ばなければ二度と会えない気がした。
私は、
少しためらってから、
その人の名を、小さな声で呼んだ。
「……ねえ」
それだけだった。
相手は振り返った。
驚いた顔をして、
でもすぐに、柔らかく笑った。
「わ、久しぶり……!」
その瞬間だった。
私の中に積み上げてきた“過去”が、音を立てて崩れていったのは。
きっと、私は「再会」をどこかで理想化していた。
時間が経って、傷が癒えて、
もっとちゃんと話せるかも、って思っていた。
だけど、現実は違った。
声をかけたことで、
自分がどれだけ過去にしがみついていたかを知ってしまった。
思い出は美しい。
でも、それは「そのまま」にしておいた時だけ。
触れた途端、
綺麗に折りたたんであった記憶は、
ぐしゃりと音を立てて形を変えた。
会話は当たり障りなく続いた。
近況とか、仕事のこととか。
お互いの変化を笑い合って、
まるで過去がなかったように話せた。
でも私は知っていた。
この会話は、過去を埋めるものじゃない。
むしろ──“過去との別れ”そのものなんだって。
帰り道、スマホにその人から「またね」と一言届いた。
それきり、何もない。
きっと、もう何も起こらない。
それでいいと思った。
だって私は、
“声をかけた”ことで、ちゃんと自分の過去を終わらせたのだから。
たった一言で、
人の関係は再開することもあれば、
きっぱりと幕を下ろすこともある。
でも、どちらも大切なんだと思う。
前に進むためには、静かな終わりが必要なこともあるから。
「声をかけてよかった?」
自分にそう問いかけてみた。
答えは、
少しだけ胸が痛むけれど、
こうだ。
「うん。呼べてよかった」