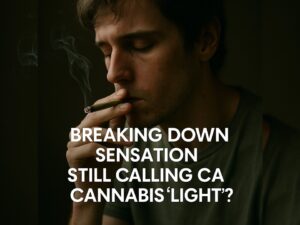彼女は、“ケア”の名を使って人の人生を奪っていた。
その笑顔は完璧で、言葉は常に礼儀正しく、
一切の“怒り”も“欲”も感じさせない。
まるで、
それが“良いこと”であるかのように。
でもそれは、
法律の裏側を這う、徹底した略奪だった。
「この方には保護が必要です」
その一言で、全てが動きだす。
医師も、裁判所も、家族でさえも、
その言葉に抗うことはほとんどなかった。
抗う必要がなかった。
──いや、抗う気持ちが、もうどこにもなかったのだ。
そこにいたのは、
親の“資産”には関心があっても、
親の“声”にはもう耳を傾けようとしない家族だった。
「じゃあ、お願いします」
それだけの言葉で、
長年の関係は、きれいに、簡単に手放された。
介護の責任は重すぎる。
正論では追いつかない現実もある。
でも、それでもあまりに簡単に、
家族という繋がりが「金づる」とされていく、
日常の風景を、今日も見てしまった。
現代社会は、“福祉”の名の下で、
とても静かに人を分断していく。
誰かの「面倒」を引き受ける代わりに、
誰かの「心」は無関心という名前の避難所に逃げ込んでしまう。
そして、その沈黙が、システムの温床になる。
ケア施設の炊飯器は、今日も同じように鳴る。
「ピッ」という音が知らせるのは、炊きあがったごはん。
でも誰も、それが誰のための一膳なのかを気にしない。
ターゲットになった老人の家族も、
最初は少しだけ心配そうな顔をしていた。
けれど、彼女の言葉に安心して、こう言った。
「じゃあ、そちらにすべて任せます」
それが始まりだった。
もう終わったことのように、
彼らは“生活”に戻っていった。
そして、その空席に、マーラの手が伸びた。
完璧な書類と、美しい手続きと、
“やさしいケア”の仮面をつけて──。
だが、欲と冷徹が手を組んで膨らんだ事業は、
たった一発の銃声で終わった。
闇と結託し、数百倍にも拡大したビジネスの果て、
彼女の物語は、誰にも看取られることなく、
静かに閉じられた。
報道は数日で風化した。
ニュースは「特殊な事件」として処理された。
でも私は、あれが“特殊”だったとは思えない。
むしろ、
あれは今の社会のかたちそのものだった。
制度の中に毒があるなら、
それを見て見ぬふりする「まわりの静けさ」こそが、もっと深い罪かもしれない。
家族が、関係を諦めたとき、
その人の未来は制度と数字に委ねられる。
愛が放棄されたところに、
福祉は“業務”として降りてくる。
「完璧なケア」──
そう呼ばれるものの正体は、誰かの沈黙と、
誰かの妥協と、
そして、誰かがいなくても気づかない仕組みの集まりかもしれない。
今日もまた、
清潔な部屋でごはんが炊かれている。
炊きあがったことを知らせる音が鳴るたびに、
私は問いかけたくなる。
その一膳は、誰のために炊かれたのか。
そして、
その“誰か”の顔を、いったい誰が思い浮かべているのか誰も知らない……