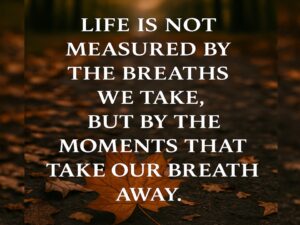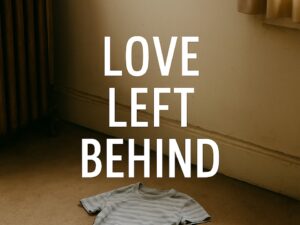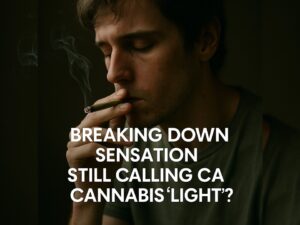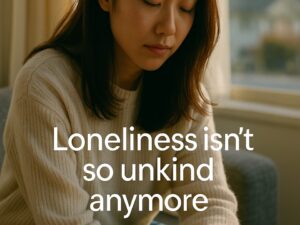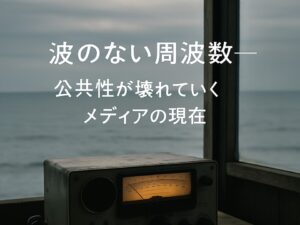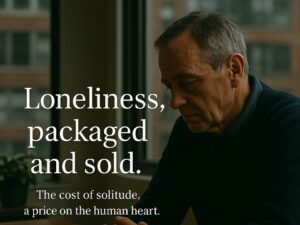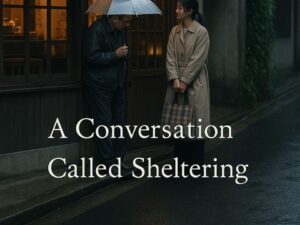被災者が「訴えられる側」になるという現実
プロローグ
誰がこの物語を予想しただろう
津波がすべてをさらったあと、
“生き残った人”たちが背負わされたのは、
悲しみや喪失だけではなかった。
──支援金の「返済請求」。
それは、あまりにも静かに、あまりにも当たり前のように、始まっていた。
本編
「無利子」「無担保」の落とし穴
あのとき、被災地の役所は言った。
「これは生活再建のための一時金です」
「無利子・無担保で、安心して使ってください」
200万。300万。その金額に救われた人もいた。
でも、それは“希望”ではなく“契約”だった。
支援の言葉に隠された小さな文字──
「5年後に返済義務が発生する可能性があります」
家を失い、家族を亡くし、人生をゼロに戻された人たちに、「その金、返してください」と言い始めたのは、同じく“公”を名乗る存在だった。
裁判という二次災害
支援金の返済に応じなかった人は、訴えられる。
家に封筒が届く。
内容証明と、訴訟通知。
「善意で借りたのだから、返すのが当たり前でしょう」でも、その“善意”に救われたのは、誰だったのだろうか。
制度か。役所か。それとも予算の数字か。
現実の復興とは何か
“被災者”という言葉には、どこか守られる響きがある。けれど、実際にはその肩書きは数年で剥がれ落ち、「債務者」「被告人」として再分類されていく。
仮設住宅も老朽化し、心の回復も追いつかないまま──「あなたには、これだけの借金があります」と告げられる。
裁判所の中で泣く人を、
誰が“守られるべき存在”と見なすだろう。
エピローグ
“守られるはずの人”が訴えられる時代に
彼女は、震災の夜に夫と息子を失った。
翌朝、泥の中に残っていたのは、ひしゃげた軽自動車と、冷えたペットボトル1本だけだった。
電気もガスもない中、
炊き出しの列に並び、タオルを乾かす場所さえなく、それでも、配られた書類に名前を書いた。
「無利子・無担保。
生活再建のための援護金です」
200万円。
それは、あの日の朝に光っていた数少ない“希望”だった。
彼女はそれで、洗濯機を買った。
子どもがいた部屋を、少しだけ片づけた。
少しだけ、生活が“戻ったように”思えた。
でも、それから5年。
彼女の元に、封筒が届いた。
差出人は「市役所 災害援護資金課」だった。
内容は、「返済のお願い」ではなく、いきなり
「訴訟通知書」だった。
被災者が、被告になる。
それが、この国の“支援のかたち”だった。
弁護士は言った。「契約ですから」
役所の職員は言った。「あなたは“支援”を受けたのですから、返すのは当然です」
彼女は何も言わなかった。
いや言えなかった。
声を出せば、泣いてしまうとわかっていたから。
法廷のベンチで、
あのとき買った洗濯機のことを、なぜか思い出していた。
静かに回る音が、やけにやさしかったことを。
この国は今、
“生き残ったこと”の代償を、請求している……..
余韻の一言
あの日「助けられた人」が、
今、「法廷で黙る人」になっている──
支援とは、何を支えているのか。
この問いを、記憶の下から掘り起こすのが、私たちの仕事だと思う。