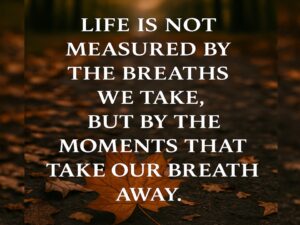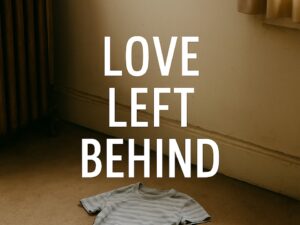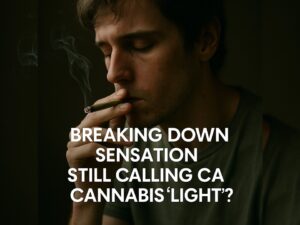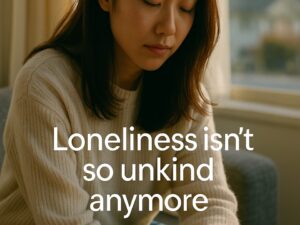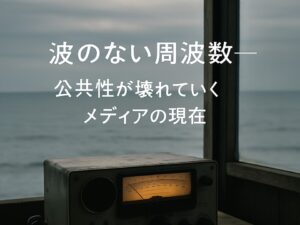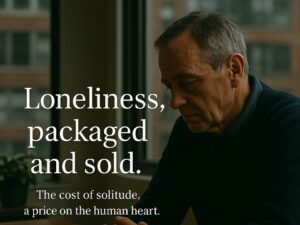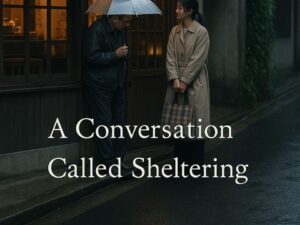朝のテレビ番組。
ブロッコリーの茎、にんじんの皮、トマトのヘタ──かつて“ゴミ”とされていた部分が、いまや“栄養の宝庫”と称えられ、誇らしげに調理されていく。
それは「工夫」か?
「優しさ」か?
いや、ふと感じる“違和感”こそが、本質なのかもしれない。
● なぜ、いま「野菜の皮」をありがたがるのか?
その背景には、異常な物価上昇という現実がある。
私たちの生活を圧迫するその事実を、あたかも**“知恵”や“美徳”**のようにメッセージへと置き換える。
まるで魔法のようにすり替えられる日常の窮屈さ。
「節約レシピ」──
そう謳いながら、テレビは**“なぜ値上げが止まらないのか”**という核心には触れない。
誰が価格を決めているのか、どんな力が背後にあるのか──その“中身”には決して踏み込まない。
つまりこれは、問題の“中身”ではなく、“我慢の仕方”を教えているプロパガンダなのだ。
昭和の戦時中、こんな標語があった。
「欲しがりません、勝つまでは」
「お国のために、節約・貯蓄・献納」
それは“痛み”を、“美しい我慢”へとすり替える装置だった。
国家が、国民の「欲望」を抑え込み、「耐えること」を“美徳”として強要していたのだ。
そして今──
「食べられるだけありがたい」
「皮まで使うのが美しい」
「捨てない暮らしが人に優しい」
これらのフレーズは、現代版の標語に見える。
戦わずして従う国民の再生産。
NHKという、“公正”を謳う放送局が、なぜこのような生活指導を堂々と流せるのか。
きっと誰もが、もううすうす気づいている。
本当に怖いのは「値上げ」そのものではなく、
その構造に、誰ひとり異議を唱えなくなった社会そのものなのだ。
この国にとって“都合のいい国民”とは、
怒る人ではなく、**「上手に我慢する人」**である。
そして今日もまた、
“皮まで食べる暮らし”は、「優しさ」として語られていく。
けれど、これは決して美談ではない。
節約は美徳か?
それとも、従順の訓練か?
野菜の皮を食べるその姿に、
わたしはふと、見えない戦時下を見てしまうのだ。
PERSOna Essayistのひと言:
“我慢”が美徳だと教えられる社会では、
本当の自由は、いつも遠ざけられていく。