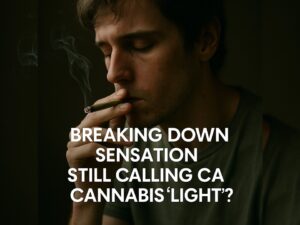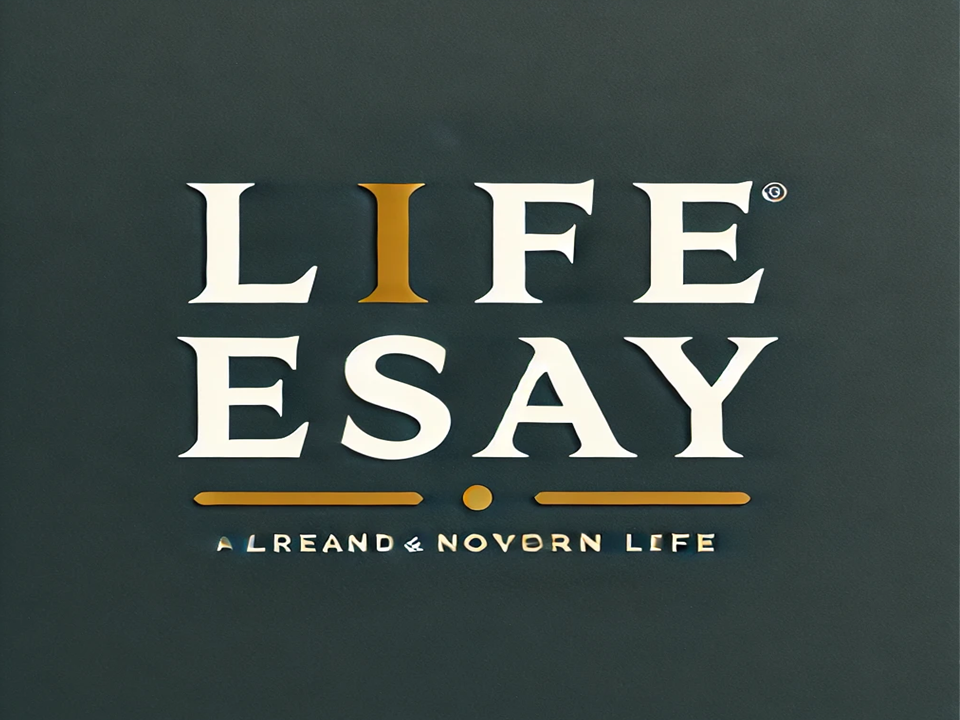
「永遠って、どれくらいのことを言うんだろうね」
彼女はコーヒーをかき混ぜながら言った。
言葉の奥に、ほんの少しの寂しさが混じっていた。けれど、彼は気づかないふりをして、窓の外を見た。
「永遠なんて、きっと存在しないよ」
そう言った彼の声には、何かを守ろうとするようなやわらかさがあった。
ふたりは長く一緒にいた。
季節がいくつも過ぎて、覚えていない喧嘩もたくさんあった。
それでも、彼女の寝癖のついた髪や、
彼の靴下の片方だけ色が違うことに、
少しずつ愛着が積もっていった。
「永遠って、たぶん“終わってから”じゃないとわからないんだよ」
彼女は笑って、カップを置いた。
「じゃあ、終わっても好きだったら、それが永遠?」
「そうかもね。でも、
私、今がすごく好きだから……もう、それでいい気がする」
その言葉に、彼は黙ったまま、彼女の指に触れた。
温度だけが確かだった。
何も約束していないのに、心は静かに寄り添っていた。
永遠の愛って、未来の話じゃない。
きっと、今日の記憶を、明日も愛おしく思えること。
ただそれだけで、人は生きていける。