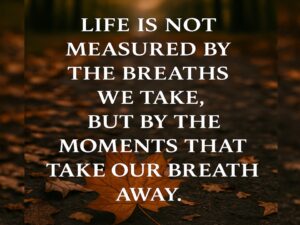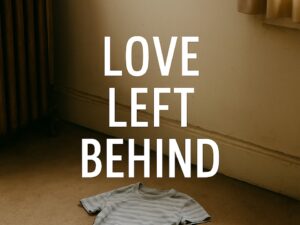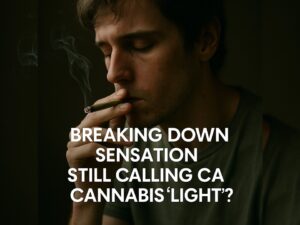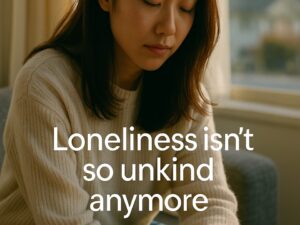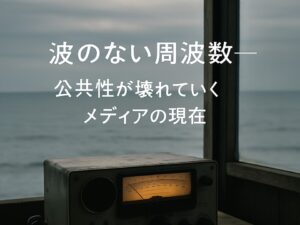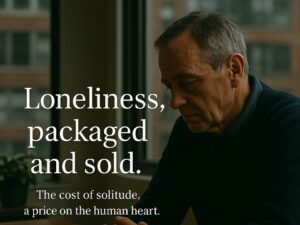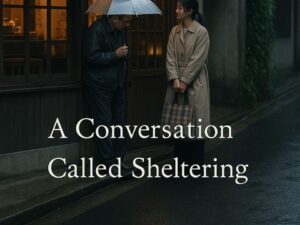―人が映した時代の記憶―
序章
2025年、日本の放送は100年の節目を迎えた。
ラジオから始まった「声の時代」、テレビによって開かれた「映像の時代」、そして今、誰もが発信者となれる「個の時代」へ。
そして、もし昭和という元号が続いていたなら――今年は「昭和100年」でもある。
奇しくも重なったこの「100」という数字。
それは単なる偶然ではなく、静かに時代同士が対話を交わしているようにも見える。
昭和が映してきたもの
昭和という時代には、エネルギーがあった。
戦争で焼かれた街に響いた、復興の足音。
高度経済成長という夢と、その果てに訪れた現実。
バブルの宴と崩壊。
激しく、迷い、笑い、涙をこらえながら、人々は懸命に生きていた。
その営みを、メディアは映し出し、時に煽り、時に支えた。
ちゃぶ台の真ん中にあった白黒テレビ。
「8時だョ!全員集合」に沸く団地の夜。
「紅白歌合戦」で年を越し、「ニュースステーション」で世界を知る。
テレビは、家族の空気そのものだった。
そこには今ではもう感じることの少ない、「生の温度」があった。
声の震え、沈黙の間合い、笑いのにじみ。
それは、確かに“人”がそこにいた証だった。
「努力が報われる」時代の幻想と希望
昭和の空には、「働けば報われる」「努力すれば必ず道が拓ける」という、希望があった。
メディアはその希望を後押しし、時に幻想を与え、時に現実を突きつける鏡となった。
笑いと涙、栄光と挫折、興奮と沈黙。
それらすべてが、映像とともに私たちの記憶に刻まれてきた。
変わりゆくメディア、問われる未来
やがてバブルが崩壊し、インターネットが生活を飲み込む。
情報は手元に溢れ、YouTuberが時代のスターとなり、AIがニュースを読む。
「この先、メディアは何を伝えるのか?」
もはや、技術の進化だけでは語れない。
映像がいかに高精細でも、人の温度を忘れてしまえば、それは“情報”ではなく“ノイズ”だ。
エピローグ
――人が映した時代の記憶
メディアの背後には、いつも人がいる。
そしてその人の“生き方”が、画面の隙間ににじみ出ていた。
戦争も、災害も、再生も。
時代に翻弄されながら、確かに何かを託そうとしていた人々の姿が、そこにはあった。
技術の進化は止まらない。
だが、私たちが本当に見たいものは、「画質」ではなく「心の像」なのではないか。
—— どんな技術で伝えるかではなく、
—— 何を伝え、どう受け取るか。
それを問い続けることこそが、
人と時代をつなぐ“物語の力”なのだと思う。