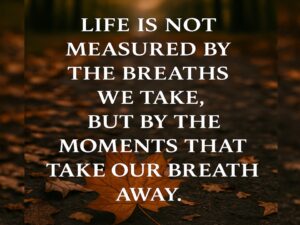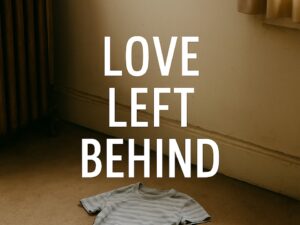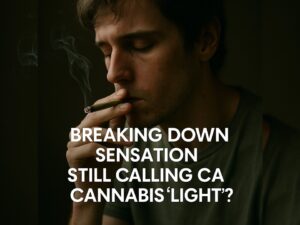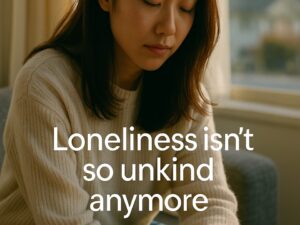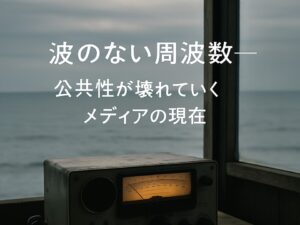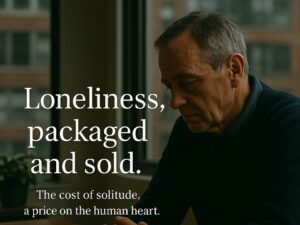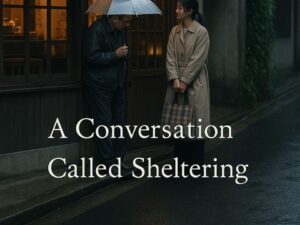導入文
「えっ、お米ってこんなに高かったっけ?」
最近、スーパーでふと感じた違和感。 パッケージは豪華でも、中身は減り、値段はどんどん上がっていく。
あの“いつもの米”が、今では贅沢品のような扱いになっている。 日本の食卓に何が起きているのか。
本文
「いい加減にしろよ、日本」 そんな声がつい口からこぼれそうになる、今の私たちの食卓事情。
最近、スーパーで米を買おうとした。 あれ?
ない。 いや、正確には「ある」けど、数が少ない。 そして……高い。
あの“いつもの米”が、ここまで値上がっていたなんて。
スーパーはどこを見ても、パッケージだけがやたらと立派で、 中身は減り、価格だけが立派に高くなっている商品ばかり。
その上、更に仕上げは容赦なく続き、消費税の上に、さらに消費税を被せ、これ以上に便乗値上げが横行する始末には驚きを隠せない。
「値上げしなきゃ損でしょ?」 そんな空気が、社会全体を包んでしまった。
大企業だけじゃない。 今や中小・零細企業までが「上げるなら今」と、価格を吊り上げまくっている。
その結果、あの“いつもの米”は、「ちょっとした贅沢品」になってしまった。
え、これが今の日本? 世界でも有数の“米どころ”じゃなかったの?
備蓄米の闇と、倒れていく米屋たち
そして飛び込んできた、衝撃のニュース。
—— 備蓄米の横流し。
冗談じゃない。
農林水産省は、代々続く米問屋たちの“静かなSOS”に、 耳を貸そうとはしなかった。
いや、正確には……見て見ぬふりをしてきたのだ。
結果、何百年も続いてきた老舗の米問屋が、 次々と静かに、音もなく倒れていく。
あの地元の人たちに愛されていた米屋が、 跡形もなく消えていく現実。
そして浮かび上がるのは、農協の“米余り”問題。
なのに、なぜか米は市場から消えて、 なぜか高値で転売されるという不可解な矛盾。
日本のコメ自給率は、実はほぼ100%に近い。 それなのに「足りない」と感じてしまうのは、 輸送・販売ルートの問題、 そして備蓄米が“特定業者”にばかり流れている、 そんな不透明な構造が放置されているからだ。
日本は2024年、食品全体で平均約6.5%の値上げを記録した。 これはコメだけではない。
小麦、食用油、調味料、日用品…… あらゆるものが便乗値上げの連鎖に巻き込まれている。
経済的“内戦”と、見えない戦場
この「経済戦争」は、もっと深いところで進行している。
ウクライナとロシアの戦争が遠い世界の話に思えないように、 日本でもいま、経済観念をめぐる“内戦”が静かに始まっている。
「誰が得をし、誰が損をするのか」
すべての値上げの裏には、“誰かの利権”が潜んでいる。
その結果、私たちの何気ない日常の「食卓」すら、 その戦場に引きずり込まれていくのだ。
国民は、怒ってるぞ。
こんな現実、誰が望んだ?
おばあちゃんがコメを研いでいた、あの台所。
炊き立てのごはんの香りに、
家族みんなが集まってきた、あの光景。
もう一度、声を大にして言いたい。
—— コメが、普通に買えない国って、なんなの。
政府も、業界も、そして値上げに乗っかってるあなたも。 今一度、考えてほしい。
私たちは、ただ「当たり前のものを、当たり前に食べたい」 それだけなのに。
エピローグ
この国のコメは、本当に未来の子どもたちの記憶に残るのだろうか?
ある日、こう言われる時代が来るかもしれない。
「え? 昔って“毎日”ごはん食べてたの?」と。
炊き立てのごはんの香りを知らない子どもたちが当たり前になる社会。
日本が“米どころ”だったことさえ、教科書の片隅でしか語られなくなる日。
それでも私たちは、まだ黙っているのか?
この国が、自国の主食を“手放す”選択をしていくことに、
何も声を上げず、見て見ぬふりをするのか?
米が消えるということは、暮らしの記憶が、文化そのものが、静かに消えていくその終わりを、
私たちはいま、自らの手で始めてしまっている事に気づくべきだと思わないのか?
不思議だとしか思えない………。