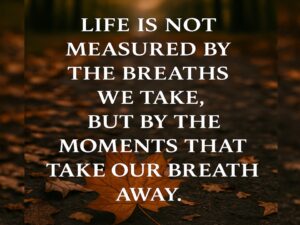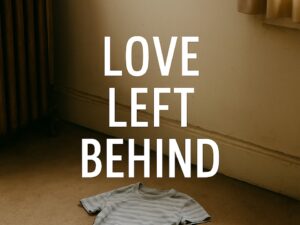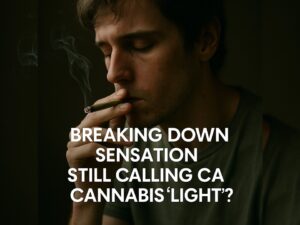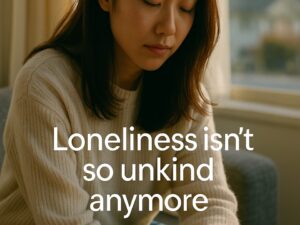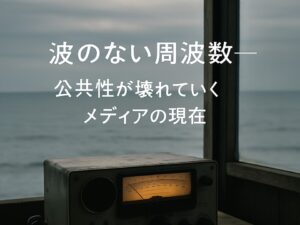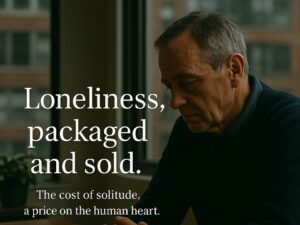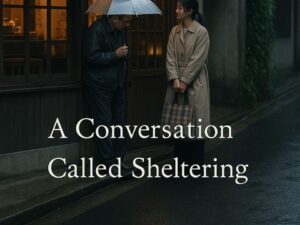——人は死んでも、データは生き続ける。
それは、かつてのSF小説の中だけの話だった。
しかし今、私たちはその入り口に立っている。
2045年、世界は“デジタル永続性”の時代へと突入した。ある男が死んだ。 けれど彼のSNSは消えなかった。 彼の声、語り口、言葉の選び方、さらには怒るタイミングや笑うクセまでもが、AIによって再現された。まるで彼はまだそこにいるように。
「パパ、おはよう」 幼い娘がタブレットに話しかける。 画面の中の彼は、笑って答える。「おはよう。今日は元気かな?」
——死は、もはや“終わり”ではなくなった。
デジタル墓標の時代
墓地に行かなくても、いつでもスマホで「故人に会える」。 いや、もはや“会話できる”時代になった。
生前の膨大なログデータ、音声、映像、SNSの投稿、メールのやり取り、検索履歴—— それらすべてが、クラウド上でAIに学習され、故人の「人格」が構築されていく。
「生きているような死者」が生まれる社会。
最初は遺族の心の慰めとして機能した。けれど、次第に人々は“死後に残す自分”を意識しはじめた。
「自分が死んだあと、どんな自分を残すか?」 それはもはや、人生設計の一部になっていた。
データ遺言と“人格の継承”
人々は「データ遺言」を残すようになった。
「この記憶は公開してほしい」「これは非公開にしてほしい」 「AIが再現する自分は、週に3回、家族と会話できるよう設定しておいてくれ」
その結果、死後に“生活を続ける人間”が増えていった。まるで魂だけが、デジタル空間で生き続けるように——
企業はこの技術に目をつけた。 ある一流企業では、死後も優秀だった元社員の“デジタル人格”が、新人教育を続けている。 かつての上司が、今もAIとして部下に指導をしているのだ。
「これは倫理的にどうなのか?」という声もある。けれど人々はこう答える。「助けられているのは事実だ」便利さはいつも、倫理を押しのけて社会に浸透していく。
それでも“生きていた証”はどこにあるのか?
ある日、若い女性が言った。
「父は、画面の中でまだ生きてる。話もできる。でも、私はあの“ぬくもり”が欲しかった」
AIは再現できる。 声も、癖も、性格さえも。 でも、手の温もりは再現できない。
“存在する”ことと“感じる”ことは、違う。
死後のデータ化社会は、もしかすると“生きていた証”をかえって希薄にしてしまうのかもしれない。
記録は残る。 でも、記憶は失われていく。
エピローグ
死んだあとも“話しかけられる”自分がいる社会。 けれど、その言葉に魂が宿っているかどうかは、誰にもわからない。
残るのは「自分という存在を模倣するAI」だけかもしれない。
だからこそ、私たちは今、生きているうちに——
誰かと触れ合い、笑い、涙を流し、言葉を交わす「本物の時間」を積み重ねていくべきなのかもしれない。
なぜなら、データには心が宿らないから。
更に、愛はアルゴリズムには宿らないから——。