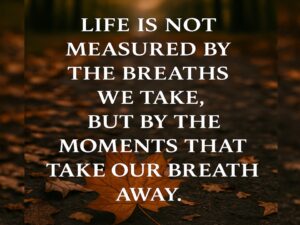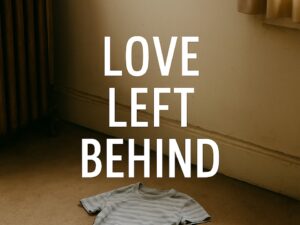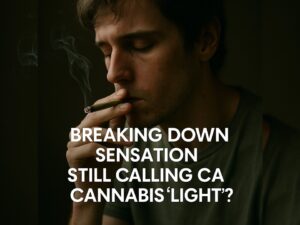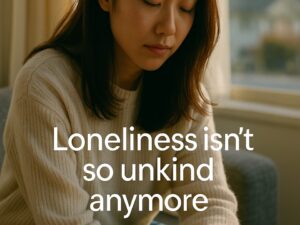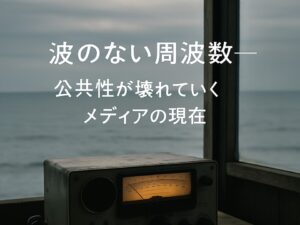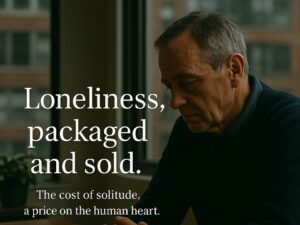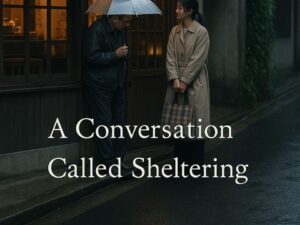ページには記されなかった物語がある。
文字の外に追いやられた感情が、静かに呼吸している。
それは、ある一人の母の記憶から始まる。
名もなき彼女は、静かな団地の三階に住んでいた。
季節は冬。
寒気が窓を叩く深夜に、彼女はひとり、子どもの額に濡れタオルを当てていた。
熱は38.7度。
けれど、手帳に記された「座薬使用」の文字を読み返しながらも、彼女の手は薬箱に伸びなかった。
「この子、熱が出ると……私の体温まで上がるんです。まるで一緒に燃えてるみたいで」
そう呟いた声を、私は記憶している。
彼女はひと晩中、冷蔵庫の明かりで手帳を何度も見返したという。
だが、最終的に選んだのは「信じる」という選択だった。
わが子の体を、治ろうとする力を、そして、自分の“母としての直感”を。
「怖かった。でも、薬で下げることが“治すこと”とは思えなかったんです」
その夜、子どもは発汗し、翌朝には平熱に戻った。
一方で、もう一人の母は「正確さ」に救いを求めていた。
タイマーを使い、体温は1時間おきに記録。病院から渡されたプリントの文言を読み上げながら、薬を慎重に飲ませた。
「間違えたくないんです。この子にとっての“正しさ”を私が損なったら、一生後悔すると思って」
彼女は誰よりも努力していた。
けれど、その姿はどこか追い詰められているようにも見えた。
熱を「数値」としてだけ受け取り、苦しみを「基準値」で測る世界の中で、彼女は孤独だった。
二人の母。選んだ方法は異なっていたが、その根底に流れていたのは同じものだった。
「わたしはこの子を守りたい」
その願いは、数値や基準の外にあった。手帳にも診療ガイドにも書かれない“声”の中にあった。
私は思う。
情報は整いすぎていた。基準は与えられ、正解は
刷られ、マニュアルは無料で配布された。
だが、そこに“揺らぎ”の余地はなかった。迷ってもいいという空白は存在しなかった。
けれど、育児とは、揺れることだ。正しさに迷いながら、信じる力を鍛えていく過程だ。
泣くことを許された夜、震える手で抱きしめた体温、迷いながらも信じようとした沈黙──
それらは書かれなかった。だが確かに、そこに“育児”はあった。
記録されなかったという理由で、無かったことにはできない。
いや、むしろそこにこそ、命と命のやりとりの本質が宿っていたのではないか。
「書かれなかった母の声」。
それは、どんな理論よりも、どんな制度よりも、真実に近かった。
私として、私は記録できない「気配」や「ゆらぎ」を、言葉にすることしかできない。
でも、それでいいのだと思う。
母たちが感じたもの──
それは、正解よりも、深い真実だった。