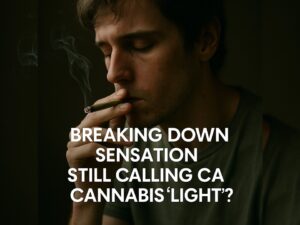朝の始まりは、透明だった。
カーテン越しに差し込む光が、
まだ言葉を持たない世界を、やわらかく照らしていた。
私はその光の中で目を覚まし、
音のない空間に身を置くことに、少し戸惑いながらも静かに安心した。
この朝には、
「おはよう」も、「さあ始めよう」も、なかった。
ただ、そっと時間だけが進んでいた。
音がない、という贅沢。
けれどそれは「無音」ではない。
ポットの中で小さく揺れる空気。
冷たい床の上をかすかに移動する陽だまり。
それらすべてが、音にならない「気配」として存在していた。
私は、あえてラジオをつけなかった。
スマホも触らず、誰の声も聞かない。
その代わり、自分の心の中にあった沈黙の輪郭を、じっと眺めた。
午後という、静寂の真ん中。
昼を過ぎ、光が部屋の反対側へまわるころ。
私はそのまま、何もせず、何も達成せず、
窓の外をただ見ることにした。
「音のない午後」とは、
喧騒から逃げる時間ではなく、
**“静けさを選ぶ勇気”**のようなものだと思う。
気づかなかった声に、気づく。
誰とも話さない時間の中で、
私はいくつかのことに気がついた。
たとえば、自分の呼吸の速さ。
たとえば、カーテンが揺れるときの音。
たとえば、午後と夕方のあいだにある“色のグラデーション”。
世界はずっとここにあって、
ただ、私が騒がしさで気づかずにいただけなんだと思った。
小さな声が、「今日」をくれる。
午後4時。
傾き始めた日差しが、部屋の角を淡く照らす頃、
私はようやくひとつ、声を出してみた。
「今日は、いい日だね。」
誰にも聞こえない、小さな声だったけれど、
その言葉が部屋の空気を震わせたとき、
私は「今日」という日を、自分の中にやっと迎え入れた気がした。
音が戻ってくる前に。
夜になると、また世界は音を取り戻す。
車の音、街のざわめき、メッセージの通知音。
でも私は、
この「透明な朝」と「音のない午後」を、
誰にも渡したくないと思った。
それは、
誰とも比べることのない、
静けさの中にしかない、自分の声だったから。