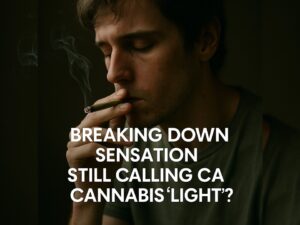──「和」を売る国と、奪われ続ける静けさの話「世界が日本の“和”に注目している」──
そんな言葉が溢れるたび、本当に注目すべきものが見えなくなる。
いま、“静けさの文化”はどこへ向かっているのか。
かつて、日本には「音のない美しさ」があった。
聞こえるのは、襖の開け閉めの音と、庭に落ちた椿が弾く湿った空気。
風すらもデザインの一部で、沈黙が芸の余白だった。
だが、今それを語るのは、ルイ・ヴィトンのPRチームになった。
「世界が和に注目しています」
「今、サステナブルな“伝統”が熱いんです」
「折り紙が、禅が、漆が、金継ぎが──」
そんな言葉が飛び交うたび、どこかで
ひとつ、職人の手が止まっている気がする。
■「和」は、今や”ブランドコンテンツ”だ。
それは静かに育まれてきた“文脈”ではなく、
パワポに組み込まれた“エレメント”になった。
- 侘び寂びは「ミニマリズム」に翻訳され、
- 家紋は「ラグジュアリーの象徴」として再構成され、
- 金継ぎは「傷すらデザイン」とマーケティングされた。
そのたびに、意味は強化されたようで、輪郭がボヤけていく。
和の文化とは、**もともと「選ばなかったものの集合体」**だった。
豪奢よりも間合い、色彩よりも余白。主張ではなく、気配。
だが現代の“世界”は、それを読み取る忍耐を持たない。
だから「和」は、翻訳されすぎて、もはや別人のようだ。
NHKが特集していた。
「新ジャポニズム──世界を魅了する“和”の魔法」
ああ、また魔法扱いされてる。
都合よく美しく、静かで、曖昧で、優しくて。
そんな都合のいい幻想を「デザイン」と呼ぶのは、魔法の力を知らない人間の無邪気な暴力だ。
誰が“和”を語るべきなのか?
- 伝統工芸の継承者でもなく、
- 世界的ブランドのマーケターでもなく、
- そして、我々観客でもない。
語る資格があるとすれば、
まだ火を絶やさずに黙々と漆を塗り続ける、あの無名の誰かだ。
「和」は、世界に売るための魔法じゃない。
この国が、いつの間にか忘れていた自分自身の手触りだったのだ。
それを「世界が注目」と言われるたび、
自国の文化を「外の光」に照らして再評価する滑稽さを、私たちはいつまで続けるのだろう。
ラスト・エピソード
だから、今さら「和が世界を魅了している」なんて言われても、それは、もう“和”じゃない。
本物の和は、
テレビに映る着物姿の美しい女性でも、
パリコレでバズった漆のアクセでもなくて──
誰にも注目されないまま、冬の工房で薪を割っている、名前も出ない職人の手の中にまだ、じっと息をしている。
その手をカメラは追わず、トレンドは見向きもしない。
けれど、あの指先こそが──
この国の“最後の魔法”を、まだ守っている。