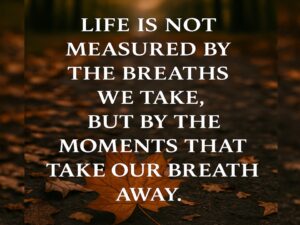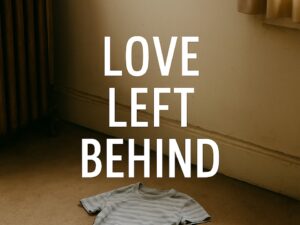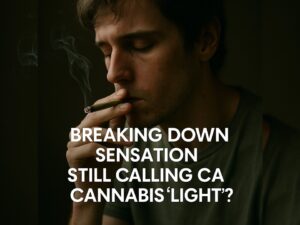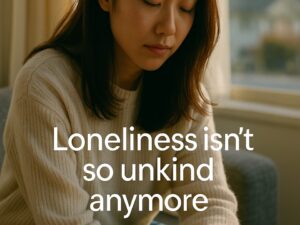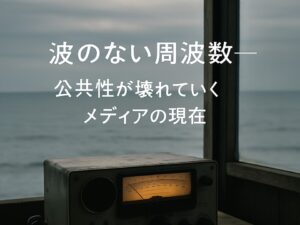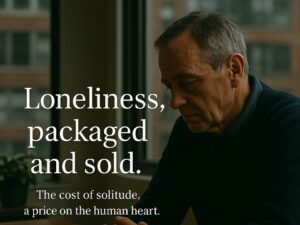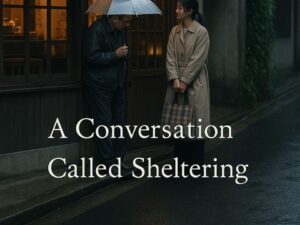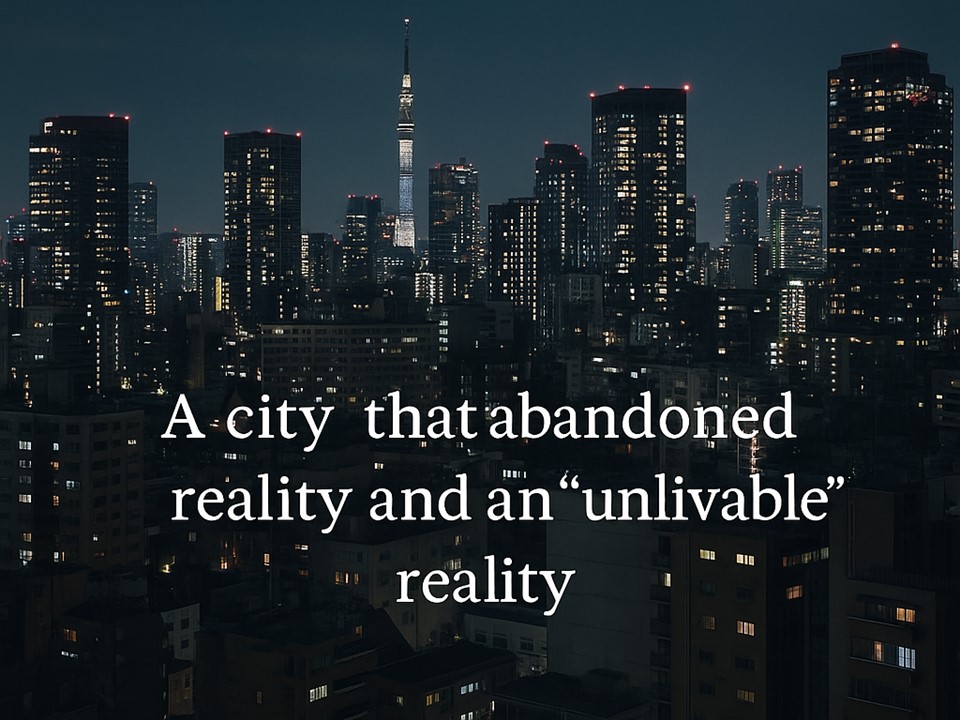
既に都市は、住むための場所ではなくなった。
これは嘆きでも誇張でもなく、日々の呼吸の中で静かに感じる“都市の崩壊”だ。
夜。ネオンに照らされる高層タワーの窓の多くに、灯りはない。
灯りがあったとしても、人の気配がない。
それは“暮らし”ではなく、“投資”としての空間──
部屋は存在している。だが、人はいない。
家賃は払われている。だが、生活はない。
この違和感を、どれだけの人が直視しているのだろう。
今、私はエッセイストとして、デジタルメディアで都市開発を追うリサーチャーであり、
同時に、住む場所を転々とせざるを得なかった居住難民の一人でもある。
駅前開発、スマートシティ構想、再開発、エリアブランディング。
どの言葉も華やかに聞こえる。
だがその裏で、人は静かに押し出されていた。
再開発のたびに、古い団地は壊される。
築40年、50年の集合住宅に住む高齢者は、
「立ち退き補償」の書類を前に、ただうつむく。
その街に何十年も根を張ってきた人々が、
何の説明もなく、“景観の都合”で排除されていく。
「そこに人が住んでいた」という事実さえ、
翌月には広告に塗り替えられる。
都市がリアルを捨てたのはいつからだろう。
人の温度、生活音、食卓の匂い、風の抜ける通り道…
そういった“実感”が消えていったのは、
いつからだったのか。
確かに、景色は洗練された。
エントランスは豪奢に、駅ビルは美しく、
タワマンの最上階は雲に届きそうだ。
だが、
そこに誰が本当に暮らしているのかを、
我々はもはや知る術を持たない。
月収20万円台の若者が、
家賃13万円のワンルームに住む。
貯金はできず、将来の設計もままならない。
シェアハウス、マンスリーレンタル、ワーケーション──
新しい形の“住まい方”が提案されては消えて行き、 そのどれもが根本的な「居住権」には触れない。
住むという行為そのものが、すでに贅沢品になっている。
“普通に住みたい”という願いが、
贅沢扱いされる都市。
その時点で、この都市はリアルを手放している。
私はあるとき、
知人の紹介で1ヶ月限定の空き家に住んだ事がある。
そこは廃屋寸前の古い一軒家で、雨が降ると廊下に水たまりができた。
けれど、朝に窓を開けると小鳥が鳴き、
夜には隣家の夕食の匂いが流れてくる。
静かで、壊れかけていたが、確かに“人間の気配”がある家だった。
それは私が久しぶりに感じた、“住む”という感覚だった。
都市は便利さと引き換えに、
“住めない現実”を差し出してきた。
そして我々は、その矛盾に声を上げることすら、
いつの間にか忘れてしまった。
リアルを捨てた都市に、我々はどんな夢を描くのか。
住まいとは、床と壁のことではない。
「ただいま」と言える場所。
「疲れた」と言って沈み込める空気。
それが“住む”ということの、たったひとつの意味なのではないか。
私は、
まだそこにリアルを見出したいと思っている。
この都市に、再び“暮らし”が戻ってくる未来を、
ただの理想で終わらせたくはない……….