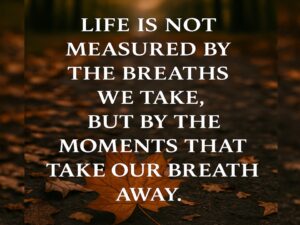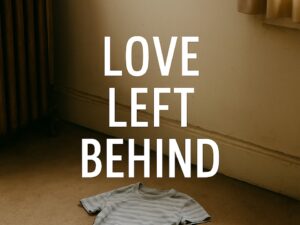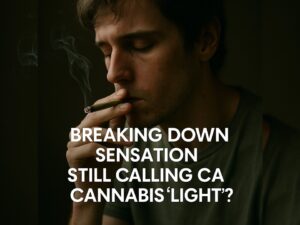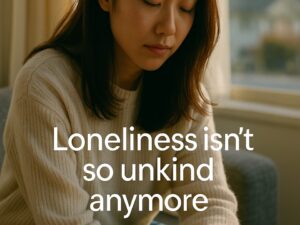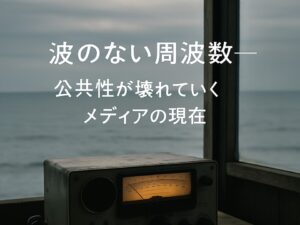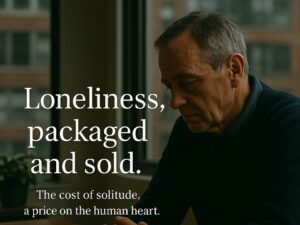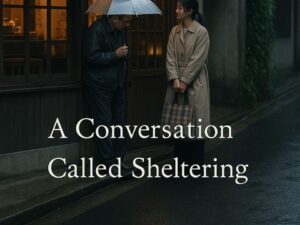「頭のいい人は、難しいことをわかりやすく説明できる人」──いつからか、それが世間の“常識”みたいになっていた。
けれど私は、その言葉を聞くたびに、どこか冷めた気持ちになる。
なぜだろう。それはきっと、
「伝わりすぎること」が、何かを薄めてしまうことを知っているからだ。
わかりやすいことは、美しい。
確かに、明快さには安心がある。
でも、それは本当に“知性”だろうか?
たとえば、哲学。
たとえば、愛。
たとえば、「生きること」。
それらを、短く、簡単に説明することはできるか?できるかもしれない。でもそれは、**“本質からの切り取り”**に過ぎない。
むしろ、すべてを語り切れない“もどかしさ”こそが、知性の証なのではないか。
私たちは時に、
「わかった気になれる言葉」で安心してしまう。
「ああ、なるほど!」と納得することで、
本来持っていたはずの疑問や、思索の火を消してしまうことがある。
言葉は、本来“問い”を引き出すためのものであって、“正解”を与える道具ではないはずなのに。
知性とは、
何かを説明しきる力ではなく、
説明しきれないことと、どう向き合うかに宿る。
「伝えたいけど、伝わらない」
「わかってほしいけど、きっと伝わらない」
その葛藤に立ち止まりながらも、
それでも語ろうとする姿勢こそが、“本当の知”なのだと思う。
だから私は、こう言いたい。
**「難しいことを、難しいまま語る人」**も、
同じくらい大切にされていいと。
説明しすぎないこと、
わからなさを残すこと、
それこそが、相手に“考える余白”を手渡す行為なのだから。
いつかわかってくれるかもしれない。
あるいは、永遠にわかられないかもしれない。
でも、それでも語る。
それでも届けようとする。
その“矛盾の中の誠実さ”こそが、
私の思う「知性の美しさ」なのだ。
エピローグ
誰かに、ちゃんと伝わることだけが、
大切なわけじゃない。
「わかり合えなかった」としても、
そのために選んだ言葉と時間は、
きっと、どこかの心に何かを残すと思っている。
だから私は、
今日も少しだけ迷いながら、書いている。
“伝えようとすること”と、
“伝わらなかったこと”の、そのあいだに、
たしかに、何かが宿ると信じて………