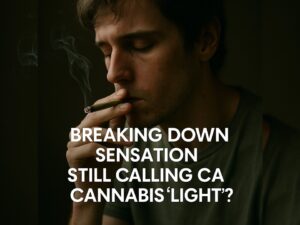1. 60年ぶりの時間
東京・神田川沿いの桜並木。
冷たい冬の風が吹き抜ける中、藤村圭一は、目の前の女性の顔をまじまじと見つめていた。

「本当に……美咲なのか?」
彼の問いに、女性は優しく微笑んだ。
「そんなに驚いた顔をしないで。あなたが帰ってくると、ずっと信じていたわ。」
それは、あまりにも自然な微笑みだった。
圭一は、その言葉に安堵しながらも、心の奥で何かが引っかかるのを感じていた。
「美咲は……こんな話し方だっただろうか?」
記憶の中の彼女は、どこか子供っぽく、少し気の強いところがあった。
けれど、今目の前にいる彼女は、ずっと穏やかで落ち着いている。
それは、ただの歳月のせいなのか。
それとも――。
2. 交わされる記憶、ずれる言葉
「少し歩きましょうか?」
美咲が提案すると、圭一はゆっくりと並んで歩き出した。
冬枯れの並木道。葉を落とした桜の枝が、まるで彼らの過ぎ去った時間を象徴しているようだった。
「圭一さん、覚えてる? この道を一緒に歩いた日のこと。」
「もちろんだとも。あの日、お前が転んで、スカートが泥だらけになったんだ。」
美咲は、ふふっと笑う。
「そんなことあったかしら?」
圭一は、思わず足を止めた。
「覚えていないのか?」
「……そうだったかもしれないわね。」
曖昧な返事。
圭一は違和感を覚えた。
「本当に、美咲なのか……?」
だが、目の前の彼女の微笑みは、昔のままだった。
3. 喫茶店「風待ち」にて
二人は、再び喫茶店「風待ち」へと向かった。
店内に入ると、美咲は懐かしそうに店内を見回した。
「この店、昔と変わらないわね。」
「そうか? 30年前に改装されたと聞いたけど。」
「ええ、でも……」
美咲は、一つの席を指さした。
「私たち、あの席にいつも座ってたわよね。」
圭一は息をのむ。
彼女の指差した席は――確かに、二人がよく座っていた場所だった。
「よく覚えていたな。」
「だって、忘れるわけないもの。」
彼女はそう言って、そっと席に腰を下ろした。
「忘れていない……?」
それなら、なぜ桜並木の記憶があやふやだったのか。
4. 60年ぶりのコーヒー
コーヒーが運ばれてくる。
湯気の立つカップを前に、美咲は微笑んだ。
「圭一さん、あなたは今もコーヒーには砂糖を入れない?」
「ああ、ブラックのままだ。」
美咲は、スプーンでそっと砂糖をすくい、自分のカップに落とした。
「昔から変わらないわね。」
圭一は、試しに訊いてみた。
「お前は……今も砂糖を2つ入れるのか?」
彼女は、一瞬だけ動きを止めた。
「……ええ、そうね。」
カップの中で、スプーンが静かに回される。
その動作を見つめながら、圭一の胸にはまた一つ、奇妙な違和感が積もった。
「美咲は、砂糖を入れたことなんて一度もなかったはずだ。」
5. ふと漏れた言葉
「それにしても、本当に帰ってきたのね。」
カップを持ったまま、美咲がふと呟いた。
「私……もう会えないんじゃないかと思ってたわ。」
「……すまなかった。」
圭一は目を伏せる。
「約束を果たすのに、あまりに時間がかかりすぎた。」
「……ううん。」
彼女は、ゆっくりと首を振った。
「でも、今こうして会えたんだから、それでいいの。」
そう言いながら、彼女はふと外を見た。
雪が、静かに降り始めていた。
6. 美咲の胸に秘められたもの
「圭一さん……」
「なんだ?」
「明日も、またここで会える?」
彼は、迷わず頷いた。
「もちろんだ。」
彼女の顔が、安心したように和らぐ。
「よかった。」
その言葉に、圭一は不意に不安を覚えた。
「美咲……何か、言いたいことがあるのか?」
彼女は、静かに微笑んだまま、首を横に振った。
「いいえ。ただ……今はまだ、何も言いたくないの。」
「……?」
「でも、すぐに話すわ。明日、またここで。」
その言葉が、どこか不安げに聞こえたのは、気のせいだったのか。
圭一は、その場では深く考えずに、美咲の手をそっと握った。
そして、彼はまだ知らなかった。
――翌日、彼女が約束の場所に現れないことを。
(第3章へ続く)
ハッシュタグ:
#昭和レトロ #喫茶店の時間 #運命の再会 #日本の情景 #ラブストーリー #珈琲と恋 #過去と現在 #着物美人 #静寂の会話 #時を超えた愛