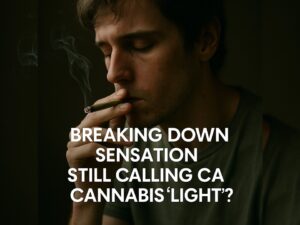素敵な日曜日の朝に贈る『今日のShort Story』
都会の喧騒から少し離れた静かな住宅街。その一角にある小さなカフェは、古いけれど温かみのあるインテリアに包まれ、いつも常連客で賑わっていた。
窓際のテーブルで、私の両親は何十年も変わらず、毎週末になると同じ時間に並んで座っている。二人の間にはコーヒーの香りが漂い、周りのざわめきの中で何かが穏やかに流れていた。
私にとって、その風景は当たり前のものだった。両親が揃ってコーヒーを飲みながら笑い合う姿。
それがどれほど特別なことか、考えたこともなかった。
私は結婚に失敗して実家に戻り、毎日が何となく淡々と過ぎていくように感じていた。そんなある日、ふと母に聞いてみた。「どうして、そんなに仲がいいの?」
母は、カップを置き、微笑んで私の顔を見つめた。「仲がいい、か…。そうね、昔のことを思い出すと、ある瞬間がきっかけだったかもしれない」。
母の目に映るのは、今よりもずっと若かった頃の記憶。何も変わらないように見えた日常が、一瞬にして変わったある日のことを語り始めた。
「あなたがまだ小さかった頃、私は大病を患って、もしかしたらこの先、視力を失うかもしれないって言われたの。お医者さんは最初にお父さんにだけ説明してくれたの。視力を失うかもしれないって話をね」。
その瞬間、母の表情は少し曇ったが、すぐに柔らかい笑みが戻った。「お父さん、そんなことを聞いて、何を言ったと思う?」
「さぁ…心配したんじゃない?」私はそう答えながら、母がどんな話をするのか予想もつかなかった。
「お父さんね、泣きながらこう言ったの。『僕には目が二つあるから、一つ奥さんにあげてください』って。看護師さんが後で私にそのことを教えてくれたんだけど、それを聞いた時、私は彼を一生信じていいって思ったの」。
私は、カフェのざわめきの中でその話を聞き、しばらく黙っていた。こんな日常の中に、そんな深い瞬間が隠されていたなんて思いもしなかった。ありふれた毎日だと思っていた両親の姿には、実は誰も見えない強い絆が存在していたのだ。
「それでね、その後の話がもっと面白いのよ」と母は続けた。「お父さん、ずっと目のことを気にしてたんだけど、結局私は手術して、目が見えるようになった。でも、それ以来お父さんがやたらと視力に詳しくなって、家族の目をすごく気にするのよ。目薬をこまめに差せとか、部屋の明かりをもっと明るくしろとか、私よりも私の目を大事にしてるのよ。おかげで、私もお父さんも、今でも視力はバッチリ!」
その話を聞いた瞬間、私は思わず笑ってしまった。そんなささいな日常の出来事にも、父の愛が溢れていたのだ。何も特別ではないように見える日常の中で、彼らは互いに見えない絆で支え合い、そして気づかないうちに、その絆が日々の小さな行動にまで染み込んでいた。
それは、ドラマチックな愛の物語ではない。日常に溶け込んだ、小さな奇跡のような愛だった。視力の危機を通じて、彼らの間に生まれた「目を大切にする」という習慣は、ただの健康管理ではなく、彼らの絆そのものだった。
私は、そんなありふれた日常の中に隠れた愛の形を知り、何気ない瞬間の裏側にあるものをもっと見逃さないようにしたいと思った。愛は、特別な場面でだけ輝くものではなく、いつも私たちのそばに静かに息づいている。
両親がカフェで並んで座り、笑い合いながらコーヒーを飲むその姿。その背景には、見えないけれど確かな愛の物語が流れていた。それに気づいた時、私は自分が何を求めていたのか少し分かった気がした。
この物語では、日常の中に隠れた「愛の真実」に焦点を当てました。カフェの中の静かな一日、何気ない親子の会話、その背後にある深い絆が、見過ごされがちな日常に潜む感動を引き立てています。