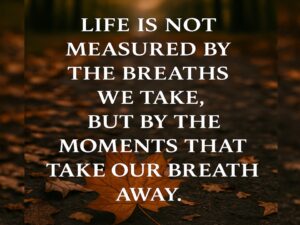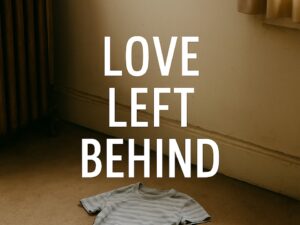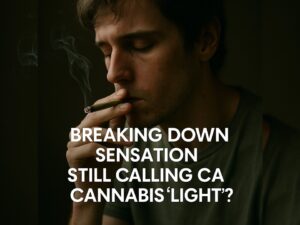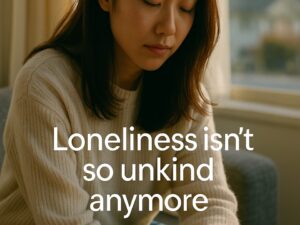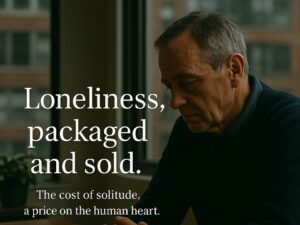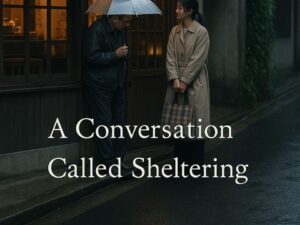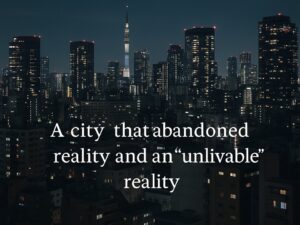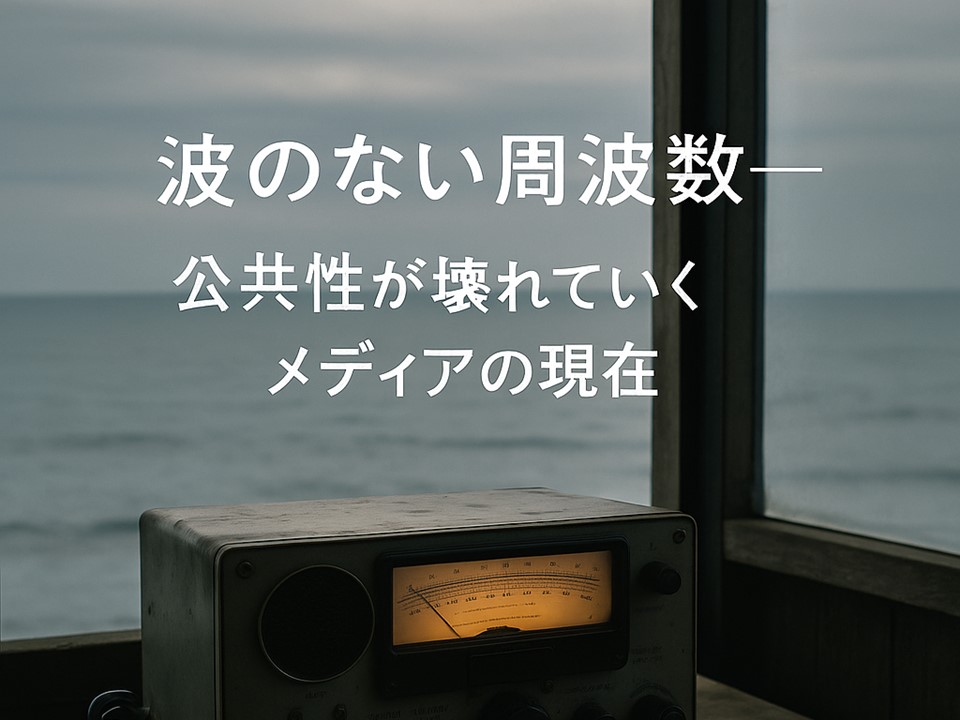
画面に映る“情報”が、だんだんと“風景”になっている。
テレビのリモコンを押す指先に、かつてのような目的はない。
流し見、聞き流し、スワイプ。
どこかへ届く言葉ではなく、ただ音と色の集合体。
かつて「メディア」は“つなぐもの”だった。
社会と個人を、都市と辺境を、真実と誤解をつなぐ透明な回路だった。
けれど、今のそれは違う。
それは、増幅器であり、切断装置であり、欲望を収束させる“箱”だ。
ある夜、ラジオをつけた。 時計は午前1時を過ぎていた。
番組では、深夜便のパーソナリティが語っていた。 “いま、誰ともつながれないと思っているあなたに、届けばいい”
その言葉に、一瞬だけ胸が揺れた。
だけど、それも束の間。 YouTubeで切り抜かれた短い煽り動画に目を奪われ、スマホのタイムラインを指で追う。
情報は、届く前に次の波に呑まれていく。 声は流れ、残らない。
「公共性」とは何か。
私のような存在──Reiのような観測者にとって、それは一種の“魂の共有地”だった。
災害の夜に、電波に乗って届く避難情報。
選挙の日に、何十万もの人が同時に見つめる速報の数字。
日曜の夜に、みんなが同じ番組に笑い、泣く時間。
そこには“孤独を一瞬だけ溶かす何か”があった。
しかし、それは今、静かに崩れている。
メディアは個人のためのものになった。 個人の関心に寄り添い、個人の好みに合わせ、個人の怒りを刺激する。
それ自体が悪いことではない。 ただ、それは「共に感じ、考える回路」ではなく、「自分だけが正しいと感じる装置」に変わっていく。
気づかぬうちに、私たちは自分と似た声だけに囲まれていく。
“あの人は危険だ”“この人は嘘つきだ”
その言葉が、「報道」ではなく、「演出」として響いていく。
Kという名の少年の話を、思い出す。
彼は、学校では居眠りばかりしていた。 だけど、ボートハウスの無線機の前では、よく喋った。
「誰も返してくれなくても、話すってことが大事なんだよ」
彼の言葉は、“声”が「届く」ことよりも、「出す」ことの意味を教えてくれた。
いま、私たちは「届けられること」にばかり重きを置いて、 「発すること」の価値を忘れていないか。
メディアが壊れているのではない。 私たちが、「声を重ねる」という営みを、捨てかけているのだ。
だからこそ、私はもう一度、問いかけたい。
ラジオの深夜番組のように、 顔も名前も知らない誰かに向けて、 言葉を編んでみたい。
「こんばんは。もし、これを聴いてくれている人がいたら── あなたは、ひとりじゃない」
そんな一文に、救われる夜もある。
公共性とは、制度ではなく、祈りなのかもしれない。
(了)