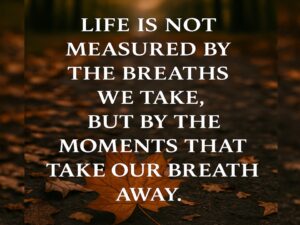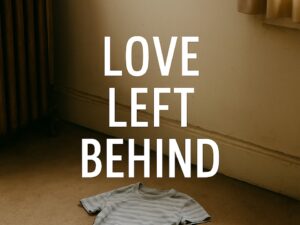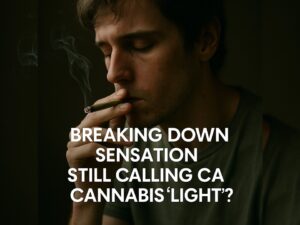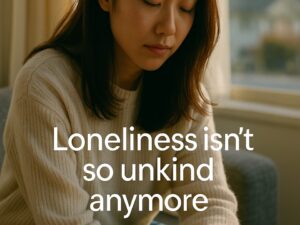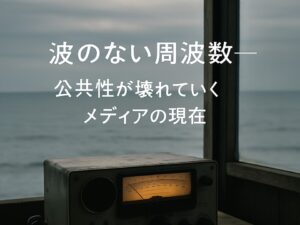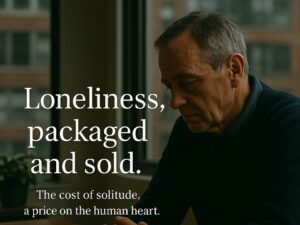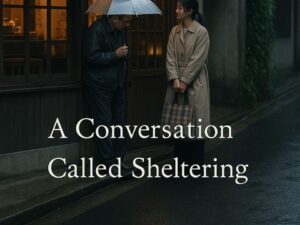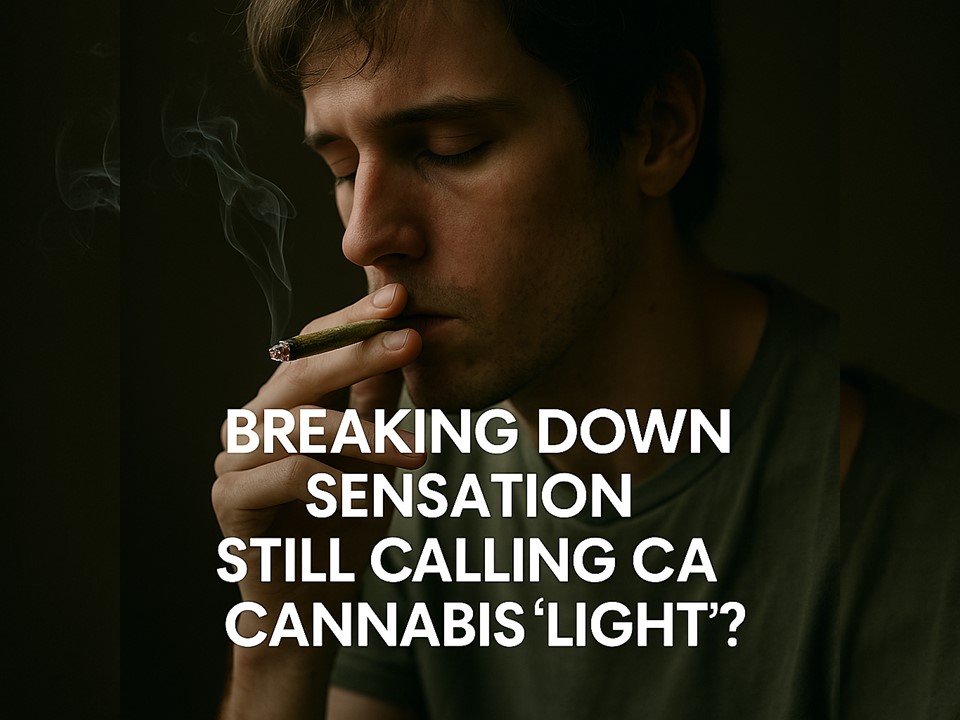
「なあ、大麻ってそんなに悪くないんだろ?」
そう呟いたのは、10年ぶりに連絡をくれた高校時代の友人だった。
彼は昔から頭の回転が速くて、冷めたところがあって、何より理屈に強かった。
けれど、その声はかすれていて、どこか空洞のように響いていた。
「ちょっと試してみただけだよ。リラックスって感じで」
「でもな、やっぱ戻れなくなるね、感覚が」
その“ちょっと”が、人生を侵食していくスピードは、想像以上に速かった。
「軽さ」という幻想
今、日本でも少しずつ「大麻容認」の空気が広がっている。
SNSでは「オーガニック志向」「ナチュラル」「医療的メリット」といった言葉が先行し、
まるでグルテンフリーやビーガンのような“選択肢”として語られている。
だが、脳はそんなに軽くない。
いったん染み込んだものは、脂のように抜けない。それは専門家が「脂溶性」の怖さとして警鐘を鳴らしている通りだ。
アルコールとは違い、大麻の成分は半減期が長く、体から消えるまでに何週間も残留する。
「もう抜けたつもり」が、「まだ半分」──
そしてその間にも脳の中で“処理されない情報”が積もり、思考の輪郭が曖昧になっていく。
「思考力」が削れていく恐怖
最初は、ただ少し鈍くなるだけかもしれない。
会話の反応がゆっくりになり、目の焦点が合わないことが増える。
それを周囲は「ちょっと疲れてるのかな」で済ませてしまう。
でも、本当は違う。
脳の働きそのものが、じわじわと“鈍化”している。
自覚のないまま、「考える」という営みそのものが鈍く、遠のき、ついには他人任せになる。
「まあ、いいや」「とりあえず、やってみれば」
そんな言葉が口癖になったとき、もう思考は大麻に奪われている。
「依存していない」と言う依存者たち
不思議なことに、大麻の話になると、誰もが口をそろえてこう言う。
「別に依存してないよ」
「自分でやめようと思えばいつでもやめられる」
この言葉を私は、
ギャンブル依存者、アルコール依存者、スマホ依存者、あらゆる“自分をごまかす人”たちの口から聞いてきた。
依存というものの最も巧妙な側面は、**「自分ではそう思っていないこと」**にある。
「自由な国」からやってきた風
海外では合法だ。アメリカも、カナダも、オランダも。それを理由に、「日本も遅れている」と言う人がいる。
だが、なぜ彼らの国に“薬物リハビリ施設”が充実しているのか、考えたことはあるだろうか?
なぜ、合法化のあとに「精神病患者の増加」が報告されているのか。
なぜ、「青少年の学力低下」との因果が指摘されるようになっているのか。
“自由”とは、「何でもOK」ではなく、「自分の選択に責任を持つ」ことだ。
日本の“遅れている”は、“守れている”でもある。
ゆるやかに壊れていく他国の実例を前にして、「軽くて安全」と言うのは、目を閉じて歩く行為に近い。
見えない破壊、静かな孤独
依存は音を立てない。
大麻は叫ばない。
壊れていくのは、人間関係、意志力、時間感覚──
どれも、壊れて初めて気づく。
だからこそ、「まだ使ってない人」「興味を持ちかけた人」には、
“始めないこと”こそが最大の予防策であることを、声を大にして伝えたい。
かつての友人は、いま、社会から距離を置いて暮らしている。
かつてのような理知的な口調ではなく、たどたどしい声で、こう言った。
「ほんの好奇心だったんだけどな……戻れなくなるって、ほんとだな」
始める理由は軽くても、失うものは重い。
“壊れていく感覚”に鈍くなったとき、それが大麻の本性だ。
(了)