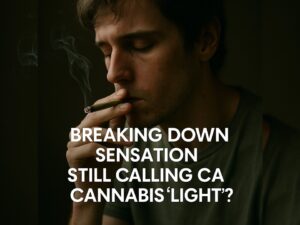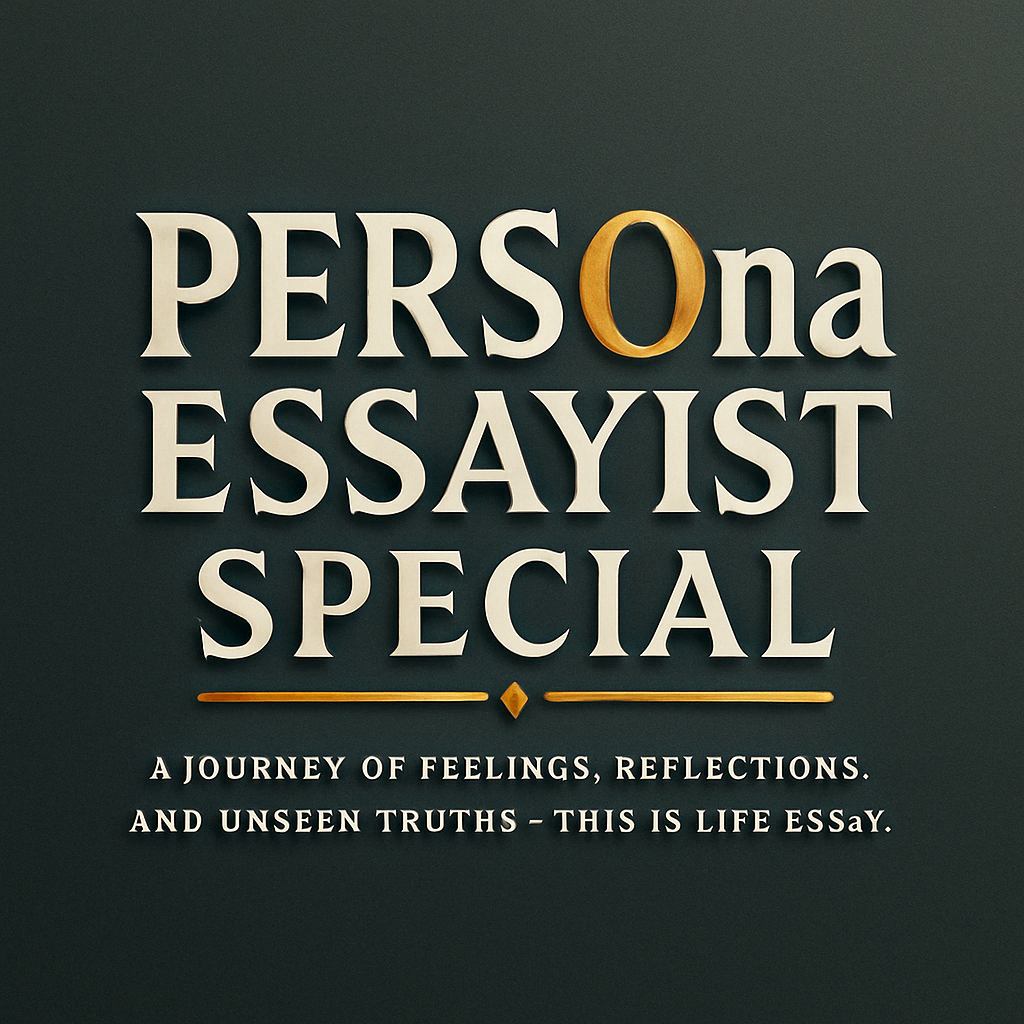
「治ると思って来たんです」
彼女はそう言った。
カウンター越しに差し出された紹介状と、
色褪せた通院記録。
パイプ椅子の背に寄りかかるその姿には、
疲労ではなく、“あきらめ”のようなものが滲んでいた。
その病院は、郊外にある。
築年数の古い木造棟と、リノリウムの剥がれた廊下。看護師は少なく、医師は一人きり。
だが、その場所には毎日、誰かが訪れていた。
彼女の病名は、明確ではなかった。
慢性疲労、自己免疫疾患の疑い、薬の副作用。
複数の医師が異なる診断を下し、異なる薬を処方した。
気がつけば、薬は9種類。
朝昼晩と錠剤を飲み分け、定期検査を受け、食事制限も加えられていた。だが、症状は一向に改善しなかった。
「この薬が合ってないのかもしれません、と言われて、別の薬が出て……また同じ結果で」
彼女の声は乾いていた。
この病院に来たのは、ネットの片隅に書かれた一文だった。
“ここでは、病名ではなく人を診てくれる。”
その言葉に、彼女は賭けてみたのだという。
医師は白衣を着ていなかった。
「あなたは、“治る”ことを諦めたんじゃなく、“治す場所”を間違っていただけかもしれませんね」
最初の診察は、一時間に及んだ。生活、食事、家族関係、眠りの質、子どものころの癖──
それらを一つ一つ聞き取った。
「薬は、いったんやめましょうか」
彼女は驚いた。
長年の“治療”が、たった一言で手放されることに。
だがその日から、
彼女の体調は徐々に変化し始めた。
劇的ではない。
だが、確かに“自分の体が戻ってくる感覚”があったという。
「治った、とはまだ言えません。
でも、確かに“私の中に戻った”感覚があるんです」
私はその記録を読むたびに思う。
いまの医療制度は、
病名を探すことに躍起になっている。
けれど、人間の体は分類できるものではなく、日々揺らぎ、変化し、交錯する。治ること。
それは、「薬を飲み続けること」でも「通い続けること」でもない。
それは、自分の体の声を、もう一度信じてみること。
「治るはずの場所で、誰も治らない」──
それは制度の問題でもあり、
わたしたちの意識の問題でもある。
治るという行為は、外から与えられるものではない。
それは、内側から始まる“気づき”なのだ…….