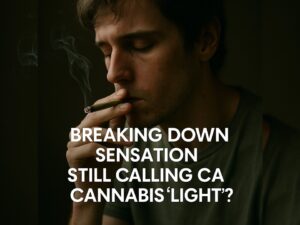人は、どこまで近づけば “近い” のか。 そして、
どこまで離れていれば “遠い” と感じるのか。
たとえば満員電車で、他人の腕と自分の腕が触れても何も感じないのに、 好きな人との間に数センチの隙間ができただけで、心が冷えることがある。
肌と肌が触れていても、心が遠くにあるとき、
その “ぬくもり” は、まるで冬のガラス越しの陽だまりのように届かない。
逆に、触れていないのに、 たった一言のメッセージや、何気ない眼差しに 全身が包まれるような温もりを感じる瞬間もある。
高校時代、初めて誰かと手をつないだとき、 「人の体温ってこんなにも生きているんだ」と思った。
そのときの相手とは長く続かなかったけれど、 その“手の温度”だけは、今も記憶に残っている。
ある夜、10年付き合った恋人と別れたあと、 ふと寝返りを打ったベッドの冷たさに泣きそうになった。
一緒にいた頃は、その人の寝息が少しうるさくて眠れなかったくせに。
「誰かと肌を寄せること」は、 面倒くささと安らぎを、常に同時に引き連れてくるのだと知った。
親子の関係も同じだ。
思春期のころ、母親の手に触れられるのがうっとうしくて仕方なかった。
けれど、社会に出てしばらく経ったある日、 久しぶりに帰省した夜、母が布団を敷いてくれる音に なぜか涙が出た。
言葉ひとつなくても、距離が近づくときがある。
「肌の距離」──それは、物理的な近さではなく、 その人を“受け入れる心の許容”なのかもしれない。
触れられたくないとき、触れられたくない理由がある。 でも、触れてほしいとき、言葉にはできない安心がそこにある。
都会のカフェで、恋人たちが無言でスマホをいじっている。 繋いだ手だけが、どこか懸命に “私たちはここにいる” と訴えているようだった。
「距離をゼロにしたい」──そんな想いが、 皮膚を通じてやっと伝わることもある。
けれど、それを受け取る側の “心” が、 ほんの少しでも閉じていたら、その願いは空をすり抜けていく。
思えば、人との関係は、温度調節に似ている。
近すぎれば、息苦しくなる。 遠すぎれば、孤独になる。
だから私たちは、その“ちょうどよい距離”を、 肌で、目で、声で、気配で、絶えず測り続けているのかもしれない。
「この距離で、伝わるだろうか」
「この沈黙で、許されるだろうか」
言葉にならない問いが、私たちの関係性の根底にいつも横たわっている。
Epilogue
最後に──
触れた手は、記憶に残る。 でも、触れられなかった心は、ずっと疼く。
人は、触れ合いたい生き物だ。 でも同時に、触れられることに怯える生き物でもある。
だからこそ、私たちは、肌の距離と心の距離のあいだで、 何度も迷い、悩み、そして、それでも誰かに寄り添おうとするのだろう。
触れなくても、届くものがある。 でも、触れることでしか伝わらないものも、きっとある。