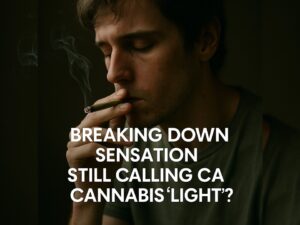昭和のオヤジ、田中五郎(たなか ごろう)は、時代の流れに逆らわずとも、自分の道を貫いてきた男だった。無駄な言い訳をせず、誰とでも肩を並べて酒を酌み交わし、言いたいことを言い、笑い飛ばしてきた。彼の辞書に「ハラスメント」なんて言葉はなかった。ただの「意見のぶつけ合い」だと思っていた。
しかし、時代は変わった。令和になり、息子が「パワハラだ、モラハラだ」と職場の愚痴をこぼす。

五郎は思わず苦笑いする。「お前、そんなこと気にしてたら仕事にならねぇぞ」。だけど、息子は真剣な顔をしている。「今はそういう時代じゃないんだよ、親父」と言い返す。
五郎は、ふと考える。

「時代の進化は便利になったが、何か大事なものを忘れてきたんじゃないか?」と。彼の頭に浮かぶのは、昔の仲間たちの笑顔と、ぶつかり合いながらもお互いを理解していた時間だった。

時代の波に乗り遅れたのか、それとも乗りたくなかったのか。五郎はただ静かに煙草を吹かしながら、遠い目で昭和の空を思い浮かべるのだった。
エピローグ:昭和の魂、令和の息苦しさ
夜の街は静かだった。街灯に照らされたアスファルトの道を歩きながら、田中はふと立ち止まった。空を見上げても、星は見えない。ビルの明かりやデジタル看板が、空を覆っていた。
昭和の頃、空にはもっと星があった。遠い昔の話だが、あの頃は世界が広がっているように感じられた。夢中で走り回ったあの頃の自分には、何かが確かにあった。家族、友人、そして自分自身。どこに向かうのかも分からず、ただ突き進む力があった。
だが、今はどうだろう。令和の時代に入って、人々は情報の洪水に飲み込まれ、何かに追われるように生きている。常に正しいことを求め、目の前の瞬間を気にして生きる。昭和の無骨さは、もうどこにもない。
「これが、進んだ文明か…」
田中は小さく笑った。進んでいるのは確かだ。だが、それが本当に幸せなのか、彼にはまだ分からない。ただ一つ分かるのは、令和のこの息苦しい空気の中で、昭和の魂はもう霞んでしまったということだ。
もう一度、足を動かし始めた。歩きながら、田中は心の中でこうつぶやく。
「ま、俺が生きていた時代は、それはそれで良かったんだろう。」
そして、足元の影が夜の闇に消えていく。昭和の魂を抱きながら、田中はこの新しい時代をただ歩き続けるだけだった。