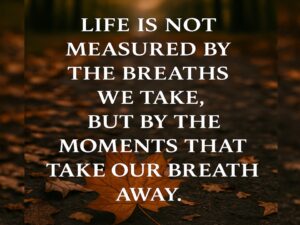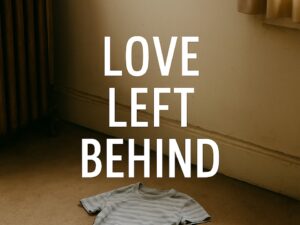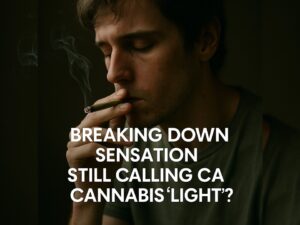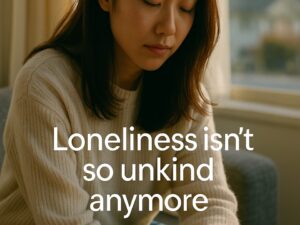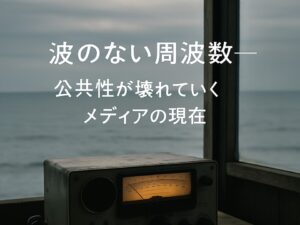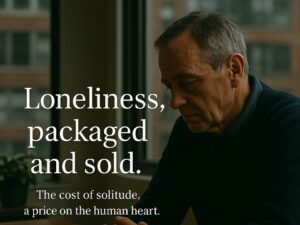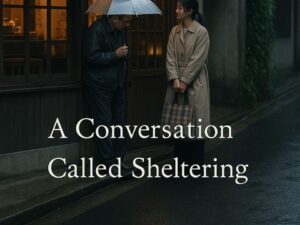かつて熊本の幣立神宮を訪れたときのこと。
正式参拝を終えた私たちに、神主さんがぽつりと語りかけてきた。
「日本人が大切にしてきた『神道』には、あるものが存在しないんです。
さて、それは何だと思いますか?」
しばし沈黙が流れた。
教えがない――。
それが、彼の答えだった。
教えがない宗教。 そんなものがあるだろうか?
世界中を見渡しても、宗教と呼ばれるものには必ず”教え”が存在する。 守るべき掟があり、破れば地獄へ落ちるという脅しがあり、救われるために救世主を待つ。
でも、神道にはそれがなかった。
戒律も、地獄も、救世主も。
なぜなら、神道は宗教ではなく、
日本人の「生き方」そのものだったからだ。
そこにあるのは、 「これは美しいか、そうでないか」という、 ただその一つの感性だった。
誰かに裁かれるのではない。
誰かに救われるのでもない。
自らの内に宿る感性に、静かに耳をすませる。
そして、自ら選び取る。
「その行為は美しいか?」
「その生き方は美しいか?」
問いかける相手は、他人ではない。
たった一人、自分自身。
教えがないから、争わない。
地獄がないから、怯えない。
救世主を待たないから、誰もが自ら歩く。
日本人は、自然と共に生きる中で、 この感性を育み、 “美しさ”を道しるべに歩んできた。
美しいか、美しくないか。
それが、私たちが受け継いできた、目に見えない羅針盤だったのだ。
時代が変わっても。 世界がどれほど騒がしくなっても。 この静かな感性だけは、 私たちの内に、確かに生き続けている。
今日という一日を締めくくるとき。 ふと胸に手をあてて、自分に問いかけたい。
「今日の私は、美しかっただろうか?」
誰にも見えなくてもいい。
答えを知っているのは、
ほかならぬ、自分自身なのだから。