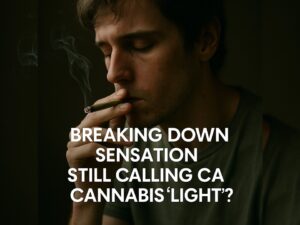僕の家は、昔から狭いキッチンがある家だった。

決して立派でも、広々としているわけでもない。でも、その小さな空間で、母は家族のために毎日料理を作り続けていた。
母の手はいつも動き続けていた。鍋をかき回しながら、次の料理を準備し、ふと冷蔵庫に振り返って足りないものを取り出す。その動作はいつも無駄がなく、まるで狭いキッチンを愛しんでいるようだった。
僕はいつも不思議だった。「どうしてこんな狭いところで、毎日こんなに美味しいご飯を作れるんだろう?」と。
ある日、母がぽつりと教えてくれた。「狭い台所がね、私を動かしてくれるのよ。頭を使って工夫しなきゃいけないから、ボケ防止にもなるし、楽しいのよ」と笑顔で話してくれた。
それから数年が経った。母は突然、体調を崩し、僕たちの前からゆっくりと去っていった。最後の入院の日、病室で母は微笑んでこう言った。
「もう、あの狭い台所には戻れないね。

でも、たくさんの思い出が詰まってるよ。あの狭い空間で、あなたたちのために料理するのが、私の一番の幸せだったんだよ」
涙が止まらなかった。
あんなに小さな空間で、母は僕たち家族にとって一番大切なものを育てていたんだ。その狭いキッチンこそが、母が家族への愛を込めて過ごした場所だった。
母がいなくなってから、僕は一度、その狭いキッチンに立ってみた。まるで母のぬくもりがまだそこに残っているかのようだった。
戸棚の取っ手、鍋の位置、すべてが母の手によって決められた配置。その狭いスペースが、いつも温かく僕たちを包んでいた。
あの日以来、僕は毎朝、あのキッチンで母の手際を思い出しながら料理をする。広いキッチンは使い勝手がいいけど、あの狭い空間には、母の愛が詰まっていたんだと気づくたびに、胸がいっぱいになる。

「お母さん、ありがとう。あの狭いキッチンで、こんなにも広い愛を教えてくれて」
エピローグ:母が残したもの
母が消えてから、あの狭いキッチンの扉の向かうたびに、まるで時が止まったかのような静けさが広がる。 あの日、母が最後にいた場所は、そのまま残されている。ほぼ今でも母が「さあ、次は何を作ったんですか」と笑いながら立ち上がるかのように。
いつか、僕は思いついて母のエプロンを手に取った。小さくして、使い込んで柔らかなその布地を顔に寄せて、ほんの少しだけ、母の匂いが残っていた。 、涙がこみ上げてきた。
「…お母さん、あの狭いキッチンでどれだけの愛情を注いでくれたんだろう」
今でも、狭いキッチンを少し不便に感じることもある。でも、その不便さこそが、母の愛の形だったのかもしれない。彼女はいつも、家族のために何かを作り、狭い空間で工夫しながら、何も言わずに頑張ってくれました。
ふと、母のエプロンのポケットに手を入れてみた。

そこには、母がいつも使っていた小さなレシピメモが入っていた。 短いメモの中に、母の手書きの文字が、まだしっかりと残っていた存在していました。